 |
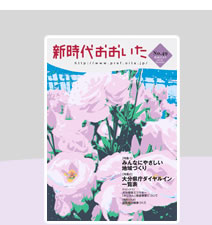 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||

| 県では、すべての県民が心安らかに生活できる地域づくりを目指しています。 しかしながら、市町村合併により周辺部となった旧町村部や障がいのある方々の中には、行政組織の変化や法律の改正で、これからの生活に不安や悩みを抱えている方もいます。 こうした課題を解決するため、県は市町村などと協力しながら、さまざまな施策を行っています。 今回の特集では、こうした「みんなにやさしい地域づくり」への取り組みの一端をご紹介します。 |
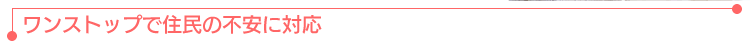
| 「平成の大合併」と呼ばれ、全国規模で行われた市町村合併により、大分県の市町村数は、58から18に減少しました。それに伴い、旧町村部では、合併後もこれまでどおりきめ細やかな行政サービスを受けられるか不安に感じている方もいます。 県では、こうした不安に対応するため、旧町村部の方々が、日常生活から生じる要望や不安にワンストップ(1か所であらゆる相談に応じること)で対応できるよう「地域総合相談支援センター」を市町村が設置する場合、運営費の補助を行っています。地域総合相談支援センターは、高齢者・障がいのある方の福祉、介護、子育て、悪質商法など、あらゆる相談に対応し、問題を解決することを目的に設けられるもので、合併新市の旧町村部に既に27か所立ちあげられています。 豊後大野市でも今年度、旧清川村、旧緒方町など6か所にセンターが設けられました。その中で、旧千歳村の地域総合相談支援センターを訪れました。センターに勤務する広瀬理恵さんは、看護師、社会福祉士の資格も持っており、昨年まで、在宅介護支援センターで住民の健康相談や介護支援などに取り組んできました。千歳に住む80歳以上の高齢者を昨年1年間で全て訪問したという広瀬さんは、新しい職場となったセンターでの活動状況について「今は、地域見守りネットワーク運営協議会を組織し、地域や個人の要望、課題を整理しながら、それに対応していける体制づくりに取り組んでいます。協議会のメンバーは、民生委員、老人クラブ、医師、小学校長、行政、福祉団体などからなり、お互いに情報交換や意見交換を行い、個人や家族が抱える問題を地域の問題として、迅速・効果的に対応できるようになることを目指しています。 千歳地域は、お茶を飲んだり趣味の合う人が集まる『いきいきサロン』が25グループできています。こうした場に積極的に顔を出して、看護師の技術を生かして健康チェックを行ったり、民生委員の会合に顔を出すなど、地域の方の声にできるだけ耳を傾け、信頼関係を築くように心がけています。もちろん、高齢者や障がいのある方の訪問活動も行っています。わたしは、千歳で生まれ、現在、こうした仕事に従事していますので、少しでも地域の人の悩みや問題解決に役立つように頑張っていきたいです」と力強く語っていただきました。 |
 広瀬理恵さん   |
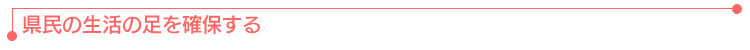

| マイカーの普及や過疎化の進行により、県内の公共交通、中でも路線バスの経営は厳しさを増しています。こうした路線バスは、地域住民の生活に欠かすことができないため、県では国や市町村と協調して路線の維持や車両購入に係る経費を補助しています。合わせて、合併新市の旧町村部の公共交通の確保のため、従来の交通体系を再編し、コミュニティ交通に取り組む市町村やバス路線廃止に伴い、代替バスを運行する市町村に対する助成も行っています。 県内では、杵築市や宇佐市などが合併を契機としてコミュニティバスの運行を始めました。その中で宇佐市では、公共交通の空白地の解消を目的に市コミュニティバス「ふれあい号」の運行を7月から19路線で開始しました。バスの利用料は一律100円に設定され、全ての市民が利用できます。新規に路線が開設された高家・天津線に乗車してみました。 この路線では、車両にジャンボタクシー(9人乗り)が使用されています。利用者が定員をオーバーした場合は、無線で追加のタクシーを呼んで速やかに対応しているそうです。始発のバス停では、他に利用者はなくさびしい状況でしたが、2つ目のバス停で早速、高齢者の方が乗り込んできました。「今日はどこにいくのですか」と尋ねると「四日市に買い物に行くんよ。今までは、タクシーを使いよったけど、バスのおかげで助かるわ」との返事。バスは、緑がまぶしい宇佐平野の田園地帯をゆっくりと抜けて、集落の狭い路地に入っていきました。住民のためにバス停までの距離を短かくしたいという配慮がうかがえます。停留所に止まるごとに乗客は増え、バスはほぼ満員状態に。中では乗客が世間話に花を咲かせています。「集落の中を走ってくれるから、バス停まで歩かんでいいし助かる。近くにお店もないので、わたしは皆勤賞で利用しよるよ」と、バスに感謝する声が続きました。 コミュニティバスを担当する宇佐市企画課の本浪亮さんは、運行にいたるいきさつを語ります。 「市町村合併により、住民サービスの部分で市民の皆さんに我慢していただくことも多く、新たに何らかのサービスを提供したいという思いがありました。高齢者が増え続ける中、日常生活を送るうえで交通の便を確保することは大切です。そうした中で、民間路線バスのない地域と市役所や病院、商店街などを結ぶ、今回のバス運行につながりました。路線や停留所の設置場所などを決める際には、地元の区長さんらにも協議し、できるだけ要望に応えました。 お年寄りがこのバスを利用することで積極的に外に出て、社会と接点を持ち、家に閉じこもらず元気に生活していただければと願っています」 バスから降りた住民は、談笑しながら軽い足どりで商店街に消えていきました。 |
 宇佐市企画課の本浪亮さん |
 |
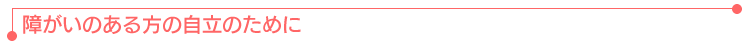
| 今年4月から障害者自立支援法が施行されました。この法律では、身体、知的、精神の3区分であったサービスが一元化され、就労支援が強化されると同時に、安定的な財源確保のため、利用したサービスの量に応じて原則1割の自己負担が求められるようになりました。県では、その影響を調べるため、2回にわたり施設利用者などへのアンケートを実施しました。その結果、負担増を理由に通所授産施設や児童デイサービスの利用をやめたり、控えたりする方が、かなりいることが分かりました。そこで県では、市町村と協力して10月から、通所授産施設を利用するたびに奨励金を給付したり、児童デイサービスの料金を法施行前の水準に軽減するなどの、独自の支援策を行うこととしました。 また、10月から障がい児施設の負担金が大幅に増加するため、負担増の半額を軽減することとしました。 障がいのある方の生活は、法律の施行でどのような影響を受けているのでしょうか。別府市にある社会福祉法人「太陽の家」を訪ねました。ここでは、およそ800名の障がいのある方が、授産施設での訓練や共同出資会社、協力企業などで就労しています。通所授産施設の電子科でICの外観検査や電子関係の部品加工に従事する糸永要一郎さんにお話を伺いました。糸永さんは、別府市内で両親と生活し、授産施設に週5日間、通っています。スポーツ観戦が趣味と答える糸永さんは、電子科に10年以上在籍し、仕事に熟練したリーダー的な存在です。 「障害者自立支援法が施行されて、利用料で1か月に約8,000円支払うことになりました。このほかに食費が一食あたり600円かかるようになりましたので、合わせて約20,000円を負担しなければなりません。これでは、1か月の収入の半分が消えてしまうことになりますので、お昼は弁当を持参することにしました。わたしは、両親と同居していますのでなんとかやっていけますが、自立してアパート住まいの人などは厳しい状況です」と糸永さん。 現在、電子科には、13人在籍していますが、1人が退所し、残っている人も多くは親の援助で生計をやりくりしているといいます。 「県や市町村が、独自の支援策を行うことはありがたいことです。職場では、障がいを持つ人が多いですから、気兼ねなく何でも話し合えるし、ストレスを感じることもありません。できれば、ずっとここで働いていきたいと願っています」と糸永さんは語ります。県では、今回の支援と合わせて、国に対して障がい者の負担の在り方も含めた制度の改善を要望していくことにしています。 |
 糸永要一郎さん  |
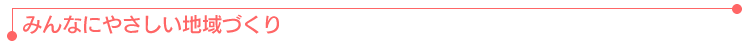
| 県では、昨年、新長期総合計画「安心・活力・発展プラン2005」を策定しました。その中では、みんなで支え合う笑顔に満ちた社会づくりの推進を目標に掲げています。県民の皆さんが大分に住んで良かったと思っていただけるよう、「みんなにやさしい地域づくり」の実現に向け、これからも努力してまいります。 |
【次へ】