本文
県内団体の取り組み事例
2.「私たちが守る。私たちの街」 (大分市西部地区総合安全対策協議会の取り組み)
3.「水と緑とやさしさの里」を基本にした子どもを守る活動について (中津市下永添子どもを守るパトロール会の取り組み)
4.「安全で安心して心豊かに暮らせるまちづくり」 (日田市光岡ワンワン・自主パトロールの取り組み)
5.「パトロールと環境整備で安全・安心まちづくり」 (杵築市塩田地区パトロール隊の取り組み)
6.「ウォーキング!健康づくりで防犯まちづくり 」(豊後大野市緒方町防犯パトロール「てくてく隊」の取り組み)
1.「笑顔であいさつ」女性の視点で地域の子どもたちを守る (大分市明治レディースパトロール隊の取り組み)
1.取組の経緯
大分市明治地区は、市の東部地区に位置し7000世帯を有する地区です。
ビックアイ(現九石ドーム)の完成やその周辺の環境整備が進む中、住宅やアパートが立ち並び人口も増えている地域です。2002FIFAワールドカップ大分開催や全国都市緑化大分フェア開催時には、おもてなしの心でボランティア活動に地区民で、精力的に取り組みました。人口増加の一方で、ここ数年、残念ながら明治地区も子ども達にとって決して、安心安全な場所ではなく不審者情報が発生するようになりました。そんな状況の中、警察や行政任せではなく「地域の子供は、地域で守る」という意識の元、女性グループ(明治婦人会・明治公民館学級生・明治小学校・明治北小学校・大東中学校の三校PTA)の情熱で、2005年「明治レディースパトロール隊」が結成されました。
発隊には、大分東警察署、大分東地区防犯協会・明治地区青少年健全育成協議会のご指導、ご協力をいただきました。現在隊員は200名です。
2.取組の内容方法
・制服
活動時には、揃いのベストと帽子を着用。ベストは、緑の蛍光色で、反射ラインも入っているので夜間でもとても目立ちます。このベストを着用することで、私たちは子どもを守るという意識がとても高まります。活動も、4年目を迎え子どもたちや地域の人に「ベスト=パトロールの人」が定着したようで、このベストを見かけると、とてもよくあいさつをしてくれます。
・隊の特徴
この隊の特徴は(1)女性だけで編成されている、(2)小グループが集まって形成されているところです。各グループが自発的に無理のない時間でパトロールを行っています。
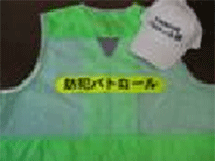
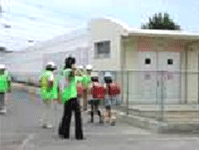
・パトロール方法
全隊で、何時何分にどこに集まって活動をするというのではなく、各グループごとに決めてパトロールを行っています。例えばPTAのお母さん達は、当番制で、登校・下校時、さらに、外で遊んでいる子ども達の帰宅時間に合わせてパトロールを行います。婦人会さん等は、買い物や犬の散歩の時やウォーキングの時などにベストを着用して、出掛けるようにしたり、また、さらに小グループを編成して、日時を決め、ゴミ拾いをしながらパトロールをしています。夕刻だったり、早朝だったりと各グループであらゆる時間帯に行います。
・笑顔で声かけ
女性ならではの、「笑顔で声かけ」を心がけています。下校時など、「気をつけておかえり」とか「おかえりなさい」など声かけをします。特に一人で下校する子どもなどには、付き添って歩くこともあります。大人の女性から笑顔で声掛けをすると答えやすいのでしょう、素直な笑顔っを返してくれたり、付き添って歩きながらいろんな話が弾みます。また、スーパーなどでは、子ども達の問題行動への抑止効果もあるのではと、「一人で来たの?」といったような声かけをすることもあります。子ども達の安全を守るだけでなく、犯罪に走らないよう見守り、あの笑顔を裏切らないよう大人が手本を示すことが大事と隊員は考え日々活動しています。
・その他の活動
地元の警察署や防犯協会などが実施する意見交換会などに参加。また、市の広報活動に協力しています。



3.成果及び課題
結成以来「無理をしないパトロール活動」を続けてきました。当時、またかと思うくら
い発生していた不審者情報も、今では、年に数件と激減し、成果は着実に上がりました。
また、他のパトロール団体も次々に結成され、その相乗効果によりさらに成果が上がる
だろうと思います。
子どもの保護者や地域の皆さんから「いつもごくろうさま」「ありがとうございます」と声を
かけていただくまでになり、安全な地域づくりに役立っているんだという誇りさえ感じてい
ます。今後も無理をしない息の長い活動を続けていきます。
参加者を募集しています!
連絡先 明治レディースパトロール隊
明治公民館内 電話 097-599-7700
2.「私たちが守る。私たちの街」 (大分市西部地区総合安全対策協議会の取り組み)
1 取組の経緯
当地区は、大分市中心地の北西に位置し、前には別府湾が広がり、背後地は、豊後一の宮原八幡社を奉る、市街地にも近く、緑と自然が豊かで理想的な住環境地域です。当協議会は、地区の交番連絡協議会に始まります。警察 署との定期的な情報交換の席で、署長から「共働きの世帯 が増加に伴い、地域安全に無関心で非協力的な人が多くなった・・・」と聞き、社会生活の多様化による警察力の限 界を感じたことから、そして何よりも自主防犯の重要性を 感じたことから、地域の安全は「私たちが守る。私たちの街」をスローガンに、平成14年8月、西部地区総合安全対策協議会を発足しました。犯罪を予防するのためには、一自治会や一校区単位で活動するよりも、広い地域で活動したほうが効果的であると考え、当協議会は、5小学校、3中校、2高校、5連合自治会、55自治会の約2万世帯にわたる地域で、67団体、約400名のネットワークにより構成されています。

2 取組の内容・方法
当協議会は、地域が広範囲に及ぶため、特に「広報啓発活動」に重点を置いています。また、一人でもできる防犯対策として「危害予防3か条」を掲げています。「見ましょう(事態の把握)、書きましょう(記憶が新しいうちにメモ)連絡しましょう(110番に)」見て見ぬふりをせずに、自分のことと思って、自らが地域を守るという強い意思をもつようにお願いしています。何事も初めは紆余曲折ですが、同じ考え、同じ気持ちの人たちが少人数でも集まれば、とにかく走って(スタート)欲しいと思います。そして問題が発生すれば、軌道修正を行うという方法をとった方が迅速に解決(活動)できると思います。完璧な体制や計画を作るよりも、「仲間とまずは行動」が大切です。
(1)「安全で住みよいまちづくり推進大会」
当会では、地域住民の防犯意識の高揚と活動の継続を目的に、毎年、「安全で住みよいまちづくり推進大会」を開催しています。本大会の特徴は、
5校区が輪番制で事務局を行い、その地域にあった大会を当番校区で開催しますので、5年に一回は地域住民が参加することになり、毎年同じ顔ぶ
れになることはありません。また、学校の先生もメンバーになりますので、固い話の後は、生徒さんの楽器演奏等のアトラクションを取り入れて、
地域住民の交流も図っています。既に、18年後の平成37年までの順番が決まっています。
(2)防犯ソングの制作
当会の防犯ソング「大分西部地区安全賛歌」を制作し、推進大会や広報パトロールで活用しています。
(3)防犯・広報・啓発パトロール
本会のパトロールは、各校区の青少協が核となり取組んでいます。また、広域であるため、各校区から募った20名の隊員で、青パト(地区防犯協
会の車両)によるパトロールを行っています。
最近特に成果が上がっているのは、「八幡安全パトロール隊」で、土曜日を除く毎日、活動を行っています。
月曜日・・先生グループ
火曜日・・交通安全協会
水曜日・・先生、PTA
木曜日・・PTA、警察OB
金曜日・・青少協、自治委員、民生委員
日曜日・・子ども会、体育協会、消防団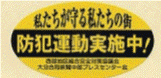


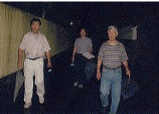
(4)一戸一灯運動
夜間の安全と安心のために、自治会単位で防犯灯や街路灯の増設に努め、電球が切れた際には、白熱灯は蛍光灯に、蛍光灯は水銀灯やハロゲン灯に
交換するようにしています。また、午後9時以降は、各家の玄関灯若しくは門灯の点灯に協力をお願いしています。
合言葉は「我が家の防犯できます。20W蛍光灯、1ヶ月110円」で、各世帯とも快く協力していただいています。また、暗がり解消のため、自治会で補助金を出し、年間5箇所ほどの家にミニ防犯灯を設置しています。電気代は各家に負担をお願いしています。
(5)不審者撃退!FAXネットワークの整備
防犯情報を早く、正確に伝達するため、まず市直営の公民館に連絡を入れ、そこから各小中学校、青少協、自治連合会ほか、各種団体にFAXで連絡が行くFAXネットワークを構築しています。

3 成果及び課題
ボランティアは、無理をしたら絶対に続きません。時間を調整して、できる人ができる時間に実践することが大切 だと思います。やはり、気負いなく、遊び心も一部にもって、楽しく、地域の実情に合わせてできれば最高だと思います。
(1)成果
パトロールを通じて、地域のことがよくわかるようになり、地域のすばらしさに出会えた。そして活動に理解してくれる人が増え、「ご苦労様」などと、地域の人からねぎらいの言葉をかけてもらうようになった。
その中で、青少年と地域の人が顔見知りになり、大人達の気持ちが若干伝わっていったのではないかと思います。
(2)課題
・時間に制約される若い層の参加を増やしたいが、敬遠されてしまう。
・地域にたくさんいる元気な団塊の世代の人たちが参加しやすい雰囲気をいかにして作っていくか。
・自治会ごとに活動の核となる民間交番「守りステーション」を設置したい。
3.「水と緑とやさしさの里」を基本にした子どもを守る活動について (中津市下永添子どもを守るパトロール会の取り組み
1.取組の経緯
私たちの町、中津市下永添地区は、旧中津市の南に位置し農村地域と新興住宅地域から成る320戸あまりの町です。 清流山国川の水系で美しい水田26町歩とおいしいお米で知られ、台地には大きな森にお宮やお寺があり、緑豊かで癒しの場として多くの人々の散歩コースになっています。私たちの町では「水と緑とやさしさの里」のテーマに向かって一致協力して先人が残してくれた自然を守り、助け合っていけるやさしい里作りを目指しています。この取組は、協議委員会、営農組合推進協議会等の役員が討議し、子供会から老人会までの各階層の人々の協力で進められています。特に、子どもたちが安全と安心を体感できる環境づくりをしていくことが重要と考え、町内の生活環境(ごみ処理、草刈、防犯意識)整備し、子どもの安全を図っています。これら活動の一環として、下校時の子どもの安全を守るため、平成17年4月9日、43人の会員でパトロール活動を始めました。


2.取組の内容・方法
(1)子どもの守るための環境整備
町内の隅々まで住民の目が行き届き整然とした町内の顔こそ安全・安心の町づくりの基本と考え、4月は水路の草刈りと溝 さらい、9月は道路のごみ拾いと草刈り(29名の班長の下、町民200名により作業)、森の木の間伐で森の保護や見通しをよくして子どもの安全を図っています。
(2)子供会によるヒマワリ植栽
子どもと大人、そして地域のコミュニケーションを向上させるために、ヒマワリの植栽をしました。750坪の雑草田を営農組合員がトラクター整地し、ここにヒマワリの種まきをし、雑草取りなどの世話をしながら、夏には見事なヒマワリ畑を作り上げました。参加した親も子もヒマワリと同じように成長したものと思います。

(3)子どもを守るパトロール活動
警察庁の「地域安全安心ステーションモデル事業」の指定を受けたことから、帽子やタスキ、Tシャツ、ジャンバーにオーバー、のぼり旗などが貸与されました。
これらのグッズを活用して、パトロールを実施しています。まず、町内を3地区に分け、それぞれ十数人ずつのチームが週1回、午後3時から午後4時まで子どもをむかえるパトロールをしています。

(4)青色回転灯パトロール車の活用
指定を受けた青パトに2人が乗車し、地区内の約7Kmをパトロールしています。 主に子どもの下校時にあわせパトロールし、夜間のパトロールも随時行っています。
(5)防犯広報
各地のごみ集積ボックスに防犯を呼びかける看板を設置し、住民や道行人に防犯をアピールしています。また、集会所の玄関や住宅の門柱にのぼり旗を立てて防犯意識を育てています。また、市から送られてくる不審者情報等を町内放送や回覧版を使い、注意喚起を呼びかけています。
(6)学校や他団体との交流・研修
平成19年12月、福岡県中間市の防犯協会と県境を越えた研修会を開催し、お互いの活動等の意見交換により、大変参考になりました。
また、随時、小学校を訪問し、校長先生等から子どもの現状についてお話しをしていただき、子どものことがよく理解できるようになりました。



3.成果及び課題
(1)成 果
ア 町内の防犯意識が高まり、安全・安心が体感できるようになりました。
イ 子どもたちと会員が仲良くなり、あいさつするようになりました。
ウ テーマ「水と緑とやさしさの里」へ一歩ずつ近づいているようです。
(2)課 題
ア もともと高齢な会員であるので、4・5年も経てば超高齢化で会員が減る一方ですので、若い人の入会を促進させる必要があります。
イ 青色パトカーによる夜間のパトロールの充実が必要です。
4.「安全で安心して心豊かに暮らせるまちづくり」 (日田市光岡ワンワン・自主パトロールの取り組み)
1.取組の経緯
光岡ワンワン・自主」は、光岡公民館、光岡小学校、光岡地区自治会が協力して立ち上げた自主防犯パトロール隊である。事務局は公民館に置く。
隊の発足当時、全国的に子どもを巻き込んだ凄惨な事件が多発し、日田市内でも児童に対する声かけ事案や不審者情報が相次いでいた為、児童生徒の安全を如何に確保するかは大きな地域課題となっていた。特に保護者にとっては切実な問題であった為、光岡小学校育友会(PTA)の要望により、平成16年7月20日に「光岡ワンワン・自主パトロール」は発足した。ワンワンパトロールは、愛犬家が日頃から行っている犬の散歩とパトロールを兼ねて行う防犯活動で、隊員自身の生活に合わせて活動できるため負担が少ない。「気楽に参加し、長く続けてほしい」という思いから、「光岡ワンワン・自主パトロール」もこの形態とした。大分県下では始めての試みである。ただし、愛犬家に限らず、ウォーキング等をしている方やドライバーのかたがたにも参加を呼びかけた。現在160名の隊員が登録している。

2.取組の内容方法
隊員は自分の生活スタイルに合わせてパトロール活動を行う。パトロールの時間や場所に決まりはなく、活動中は指定の腕章や帽子、タスキを着用する。また、きれいな環境を保つことや、住民同士の声かけが防犯上大変有効であることから、パトロール中にごみ拾いを行うことや、あいさつ、声かけを積極的に呼びかけた。パトロールでの意見集約については、定期的な活動アンケートや情報交換会を実施しており、そこで出された意見は、光岡校区対象の広報紙(光岡ワンパト通信)を発行したり、警察署や駐在所、校区内の小中高校に資料を配布している。また、車用の防犯ステッカーを希望者に配布し、パトロールに役立ててもらっており、その際市内のタクシー協会にも協力をいただいている。日常的な活動以外も、以下のような活動を実施している。
(1)防犯看板の設置…企業や事業所にも協力を求め、校区内約50箇所に防犯及び環境美化を呼びかけるたて看板を設置した。また、小学校や通学路にも子どもを守るための防犯パネルを設置した。
(2)犬の糞害防止活動…犬の糞害についての訴えは多く、校区内に約100箇所程設置した。 また、愛犬家のマナーアップを目的に「愛犬のしつけ教室」を開催した。 
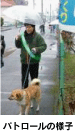



(3)自主防犯パトロール研修会の実施…日田警察署、防犯協会連合会と協力して実施。 また、犯罪に関する情報等も広報紙などで地域に提供している。
(4)各町自治会、民生児童委員、小学校育友会(PTA)、高校や「大分掃除に学ぶ会」との協力…駅や校区内の清掃活動、落書き消し、児童生徒の登下校指導・あいさつ運動 等
(5)「安全・安心ステーション」モデル地区…平成18年に指定を受け、貸与を受けた防犯用品をパトロール活動に役立てるとともに、年末夜警や交通指導などのときは、各町自治会や小学校育友会(PTA)等、校区内の他団体に貸し出している。

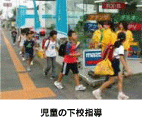
3.成果及び課題
現在5年目となるが、活動は確実に定着してきており、犯罪の抑止効果になっている。また、アンケート結果を見ると「パトロール隊に参加して町内を見る目が変わった。」という意見が多く、地域住民の防犯意識を高める上でも大変効果があるようだ。小学校児童との交流が盛んに行われるようになったことも、大きな成果である。現在、パトロール隊員はタスキや腕章、キャップを着用するようにしているが、目印になるものを身に着けておくと、児童への声かけやあいさつもしやすい。児童と顔見知りになって、毎日あいさつを交わすようになった隊員もいる。平成17年度には、小学校が「ワンパト隊員へ感謝の集い」を企画してくれた。また、児童から隊員へ感謝の年賀状を贈る活動も毎年続いている。公民館でも、隊員と児童とで交わされた年賀状を展示する「防犯が紡ぐ新春年賀状展」を開催し、今年で5年目となる。こうした心の交流にやりがいを感じて積極的にパト
ロール活動を行ってくれている方がたくさんいる。これらの防犯活動の取り組みは、光岡公民館が中心となり、各町の防犯パトロール隊や小中高校、企業、その他の団体が協力して行ってきた。防犯活動は、組織や仕組みなどのハード面だけでなく、地域住民の防犯意識や心のつながりなど、ソフト面の取り組みも同時に行っていく必要がある。今後も更にこの防犯活動の輪を広げ、「安全で安心して心豊かに暮らせるまちづくり」を目指したい。
5.「パトロールと環境整備で安全・安心まちづくり」 (杵築市塩田地区パトロール隊の取り組み)
1.取組の経緯
杵築市の東部守江湾入江に位置した塩田地区は周囲三方が川に囲まれており、その中央部に国道213号が通っています。国道沿いには大型商業施設があり、市内では最も人の集まる場所のため犯罪発生件数も多くなっています。平成16年7月に地区と警察との懇談会を開き、周辺地域の防犯対策として自主防犯パトロール隊を結成しました。同年8月には自主防犯パトロール隊「杵築を守る会」が発足しました。これには警察、行政とパトロール隊編成の5地区の代表者が集まり活動方針等について話し合いました。会議は2回/年行い情報交換を行っています。

2.取組の内容方法
(1)パトロール
パトロール方法は1回/月で第2金曜日の午後4時から午後5時に生徒の下校時間帯に合わせ、警察の協力を得て7人~10人程度で実施しています。パトロール者は区内住民が輪番制で参加し、全員で防犯意識の高揚を図っています。パトロール前のミーティングでは署員の方から防犯についての話、また隊員どうしの情報交換を行います。服装は防犯の文字入り帽子、腕章、又はたすき等を付けパトロール中であることを周囲にアピールしています。パトロール場所は商店街コース、住宅コースに分けて実施しています。商業施設では車両荒らしや自転車盗難が多いので、確実に施錠しているかをチェックしてロックされていない車両には注意書きしたチラシを入れ盗難防止を呼びかけています。駐輪場では長期の放置自転車があれば環境の低下につながるので、店側で処置するようお願いをしています。ゲームセンターなどの遊戯施設ではゲームに熱中になり置き引き等の盗難にあうので、床に持ち物を置かないように注意を呼びかけています。店内の巡回は来店者に防犯パトロールをアピールするためにおこなっています。住宅コースでは空巣による盗難が発生しているので、外出時は戸締りを忘れないように声かけをしています。留守宅では窓の鍵かけも忘れていないかチェックします。子供だけの留守番は扉の鍵かけをして、知らない訪問者がきた時は扉を開かないように伝えています。独居老人の方も同じように声かけをしています。地区内の道路には「防犯パトロール中」、「特別警戒実施中」等ののぼりを取り付けて車の運転者にもアピールしています。

(2)環境の向上
防犯灯は主に商業施設周辺に設置されていて、住宅地周辺や周囲の堤防は暗く防犯上も不十分な状態でした。これを解消するには防犯灯の増設をしていく必要があります。防犯灯の増設には高額工事費用がかかります。そこで設置箇所及び設置個数の会議を開いて順次取り付けています。現在までの新設箇所は25灯となっています。新設箇所うち3灯は電柱がない場所で工事費が倍額かかるため、行政にお願いして半額負担していただきました。ゴミ等のない綺麗なまちには不審者を近づけないと言われています。2年前よりパトロール時全員がゴミ袋を片手にゴミや空き缶など拾いながら巡回しています。

3.成果及び課題
犯罪発生件数は徐々には減少して来ていますが、自転車盗をはじめ車上ねらい、空巣などまだ多く発生しています。これらは一人ひとりが注意すれば防げる犯罪です。地域の人は勿論のこと買物客に対しても鍵かけを徹底して盗難にあわないように呼びかけて行きます。昨年の12月に杵築警察署安全・安心まちづくり協議会が設置されました。これにより自主パトロール隊の相互情報交換及び連携強化、また犯罪発生状況の把握がさらに
向上してきました。防犯灯の増設により全般に明るくなってきましたが、まだ充分ではありません。最近は朝晩暗いうちにウオーキングする人が多くいます。安全に安心して生活が出来る環境を作り、健康で明るいまちとなるように予算のゆるすかぎり防犯灯の増設をして行きたいと考えています。パトロール時の美化作業により周辺道路は大変綺麗になって来ました。以前は草むなどに多くのゴミが捨てられ掃除が大変でした。今ではゴミの投棄も活動前と比較して減ってきました。今後も"自らの街は自らまもり安全で安心なまちづくり"を合言葉に明るいまちづくりに向けて推進して行きます。
6.「ウォーキング!健康づくりで防犯まちづくり 」(豊後大野市緒方町防犯パトロール「てくてく隊」の取り組み)
1.取組の経緯
わが隊の発足経緯は、他の防犯パトロール隊と少々変わっている。昨今の少子高齢化による医療問題、生活が豊かになったことでの運動不足や生活習慣病の増加、年代間や家族間のコミュニケーション不足、子どもの運動能力の低下など住民の健康が大きな社会問題となっている。そこで、これからの時代も元気で健康的ないきがいのある人生を送るためには、みんなが自主的に、継続してスポーツや運動を楽しめる環境が必要なため、平成16年3月、総合型地域スポーツクラブ「ネスト」が設立された。 そして、平成16年11月にスポーツ関係者や有志が中心となり「ウォーキング!健康づくりをとおして防犯活動を!」と呼びかけ、”緒方町防犯パトロール隊「てくてく隊」が発足した。主たる発足理由は、治安問題からではなく、健康問題からであり、ウォーキングの副次効果として「防犯まちづくり」活動に取組んだのである。

2.取組の内容・方法
「てくてく隊」は、隊名のとおり、隊員の多くが60歳を過ぎた隊員で構成されており、「てくてく」 とウォーキングする際に、防犯と書かれた帽子とタスキをまとい、パトロールをするものである。ですから、犯罪者や不審者を追跡、検挙することが目的ではなく、路行く人に「こんにちは」とあいさつ、 声かけすることで、地域の
コミュニケーションを良好にするとともに、地域に入り込んだ「犯人」に犯行を断念させる心理的な防犯効果を狙っているものです。また、犯人から目立つよう外での活動には、必ず制 服(パトロールスタイル)を着用しています。

子どもの安全対策として、通学児童の下校時には、隊員が子どもの自宅近くまで付き添い、一人で帰宅 する子どもがないように取組んでいます。防犯活動と併せ、交通安全活動にも力を入れ、子どもへの安全指導はもとより、啓発グッズをドライバーに配布する活動などを行っています。てくてく隊のモットーは、「無理せず、活動できるときに行動する。」で、月に1回でも活動できれば、それでいいと思っています。そして、自分の生活に合わせることも大切で、仕事で昼間に歩けない隊員の一人は、夜間、自動販売機等の見守りウォーキング(パトロール)をしてくれています。できることを、できる時に、できる範囲でやることが、長続きするコツだと思います。
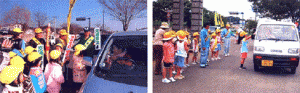
3.成果及び課題
緒方町防犯パトロール「てくてく隊」の活動も地域住民に認知され、根付いてきています。その献身的な活動は他の活動の模範となることが多く、隊長が講師として招かれ活動紹介を行うこともある。また、小中学校との交流も深いことから入学式や卒業式に隊員が来賓として招かれるともあり、益々やる気がわいてきます。 何よりも、豊後大野市内で活躍するパトロール隊の効果で、犯罪が減っていけいるような感じがし、体感治安が向上しているように思う。このまま、無理せず楽しくパトロールを続ていきたいが、隊員の高齢化が気になるところであり、新入隊員の参加を望んでいるが、画期的な方法が見つけられないところである。




