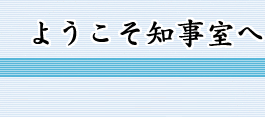
令和7年4月15日知事定例会見
動画はYouTube「おんせん県おおいた公式」へ
日時:令和7年4月15日(火曜日)13時30分~
場所:第一応接室
記者会見時に配布した資料を掲載します。

「#大分から世界へHELLO」 オープニングセレモニーについて
株式会社サンリオエンターテイメントと昨年12月に提携した連携協定に基づき、大阪・関西万博を契機とした観光キャンペーンを始め、その第一弾として、4月13日(日)、大分空港で「#(ハッシュタグ)大分から世界へ HELLO」 オープニングセレモニーを開催しました。
当日は、県内外から多くのお客様にご来場いただき、ハローキティの人気のすごさを改めて実感しました。
空港内の至る所でハローキティをはじめサンリオの人気キャラクターがお出迎えをしているデザインが施されており、「世界でいちばん、あたたまる空港」のコンセプトが伝わる内容となっています。
空港を訪れた方々にお気に入りのフォトスポットを見つけていただき、そこで撮影された写真等がSNS等を通じて世界中に拡散されることで、サンリオキャラクターとともに、本県の魅力とホスピタリティが国内外に広く伝わっていくことを期待しています。実際に、台湾出張の際にはさっそくこの話題に関心が寄せられるなど、すでに国際的な広がりを感じており、キティちゃんをはじめとする世界的キャラクターと連携した発信の力を実感しています。
また、この取組は大阪・関西万博の開催期間とも重なることから、そのタイミングを生かし、国内外への情報発信をより一層強化していきたいと考えています。
今後も、ラッピング装飾は順次完成していく予定ですので、ぜひ何度もお越しいただき、世界中で愛されるキャラクターにあふれる「大分ハローキティ空港」をお楽しみいただきたいと思います。
配 布 資 料:・サンリオエンターテイメント配信_開幕セレモニー事後レポート [PDFファイル/1.15MB]
大分県教育庁遠隔教育配信センターの開所について
昨日、大分上野丘高校内に遠隔教育配信センターが開所しました。
昨日は、臼杵高校・宇佐高校の数学と、佐伯鶴城高校・日田高校の英語の授業が行われました。この配信による授業は、対面と遜色のなく受けられるレベルで、生徒の多様なニーズに対応するシステムとなっており、学習意欲や学力の向上に大いに寄与するものと期待しています。生徒からも「先生とコミュニケーションを取りにくいと思っていたが、対面授業と差は感じなかった」、「高いレベルの勉強ができるので自分のためになると思った」といった感想を聞いています。
もう一つ、SOPといって、生徒進学支援オプションとして、遠隔配信システムを使って、今夏から、県内全域の普通科等設置高校の生徒を対象に、夏休み中の難関大学志望者向け特別授業や大学入試過去問題の解説動画コンテンツなどの遠隔配信による進学支援も準備しているところです。また、遠隔教育を受けます受講生徒に対する個別指導や、動機付け・意識改革のためのワークショップの開催、オンラインの面談についても、あわせて進めていく予定にしています。
今後とも、こういった遠隔配信により、どの地域に住んでいても、生徒の進路希望に対応した多様で質の高い教育を提供し、全国の遠隔教育の先進事例となる「大分モデル」が確立できるよう、教育委員会とともに取り組みたいと思います。
来年度には実施校を増やすなど強化を図るほか、教育現場からのニーズも聞きながら、さらなる構築を進めていきたいと思います。
配 布 資 料:・遠隔教育の「大分モデル」について [PDFファイル/405KB]
令和6年度企業誘致の状況について
令和6年度の企業誘致の状況について報告します。
企業誘致件数については、大分県長期総合計画の目標(50件)を達成する50件となりました。
新規雇用者は549人で昨年度(613人)から減少しましたが、設備投資額の603億円は、過去5年では、一昨年度(824億円)に次ぐ規模となり、着実な企業の集積に繋げることができました。
業種別では、自動車等の輸送用機械が17件と最も多くなっています。次いで、システム開発やIT関連などの情報通信が8件となりました。これは、市町村と連携して整備したサテライトオフィスなどへの進出によるものです。次いで、電気・電子の5件となっています。
地域別では、北部地域で輸送用機器、電気・電子関連分野の設備投資が進み18件、次いで、東部地域、中部地域でそれぞれ12件となっています。
今後も、県内各地に多様な業種の企業を呼び込むべく、市町村と連携しながら、用地確保等の受入環境整備を進めるとともに、首都圏での誘致セミナーの開催などの情報発信にも力を入れてまいります。
配 布 資 料:・令和6年度企業誘致の状況について [PDFファイル/91KB]
OPAM開館10周年について
平成27年4月24日に開館いたしました大分県立美術館は、本年2月に累計来館者数が500万人を突破するなど、県民の皆さまに愛される美術館として、開館10周年の節目を迎えることができました。
4月26日(土)に記念式典を予定しており、式典後は、日本文学研究者でアートにも造詣の深いロバート キャンベルさんのトークショーや、ヴァイオリニスト・廣津留すみれさんのミニコンサートを開催します。
翌27日(日)は、OPAMで北村直登さんのライブペイントや、アートの分野でも活躍されている歌手・女優の和田彩花(わだあやか)さんのトークショーなどを開催します。さらに、ガレリア竹町でも、記念パレードやアート作品の展示販売など多彩なイベントを実施します。
また、4月26日(土)から6月22日(日)まで、OPAMで10周年記念展「LINKS(リンクス)ー大分と、世界と。」が開催されます。
この展覧会では、OPAMのコンセプトである「出会いと五感のミュージアム」にちなみ、モネ、ピカソ、東山魁夷(ひがしやまかいい)らの名品に、大分の近現代美術を加え、人と人、人と作品との「出会い」をテーマとして、国内外の巨匠の作品をお楽しみいただけます。
特に5月23日(金)から展示されるピカソのゲルニカのタピスリ、つづれ織りの壁掛けは、本展覧会の大きな見所の一つであり、ぜひ、多くの方々にお越しいただきたいと思います。
配 布 資 料:・大分県立美術館開館10周年記念イベント パンフレット [PDFファイル/1.57MB]
・10周年記念展「LINKS(リンクス)ー大分と、世界と。」 [PDFファイル/602KB]
・OPAM2025LINEUP [PDFファイル/183KB]
ウェールズ政府関係者の来県について
4月26日に、ウェールズ政府から、レベッカ・エヴァンズ 経済・エネルギー・計画担当大臣をはじめとする関係者のみなさまが来県されます。
大分県では、2019(令和元)年に開催されたラグビーワールドカップを契機に、ウェールズとの交流を深めてまいりました。2022(令和4)年3月には、ウェールズ政府との間で「友好と相互協力に関する覚書(MOU)」を締結し、文化・芸術分野を中心に連携を進めております。
そうした中、大阪・関西万博において「ウェールズ・デー」を開催するため来日されるこの機会を捉えて、本県にお招きし、交流のさらなる発展や新たな分野への拡大に向けた契機としたいと考えています。
当日は、先ほどお話ししたOPAM開館10周年記念式典にエヴァンズ大臣が来賓として出席されます。その後、本県を代表する観光地や、地熱を活用した農業施設、伝統文化である竹工芸等を視察していただきます。
夕刻には、歓迎レセプションを開催し、芸術文化や経済・教育分野の方々との交流を図っていただきたいと思います。
なお、4月29日に開催される「ウェールズ・デー」には、本県から桑田副知事が出席することとしています。
万博を通じ、両地域の関係がさらに深まり、多くの分野にわたる連携が一層進むことを期待しております。
配 布 資 料:・ウェールズ政府関係者の来県についてr [PDFファイル/184KB]
農業水利施設の取水前点検ついて
昨年の台風第10号による大雨では、ため池や水路などの農業水利施設に甚大な被害が発生するなど、自然災害が激甚化・頻発化しています。
こうした豪雨等によるため池の決壊や、水路から水があふれることによる農地や家屋等への被害を未然に防ぐためには、常日頃から、ため池等を適切に保全管理しておくことが大切です。
これから本格的な田植え時期を迎えるに当たって、先月から農業水利施設の取水前点検を実施しています。
一つが、防災重点農業用ため池の点検です。
決壊した場合に家屋や人的被害の恐れがある防災重点農業用ため池1,021箇所について、ため池管理者にて点検を行い、その結果、異常が見られた場合は、ため池保全サポートセンターの専門スタッフが現地を確認し、技術的な指導・助言を行うとともに、管理者等が5月22日(木)までに、必要な補修等を実施することとしています。
二つが、農業用水路の点検です。
被災した場合に人命や家屋、公共施設に影響を及ぼす恐れがある農業用水路311路線について、5月22日(木)までに点検を行うとともに、緊急的な対応が必要な箇所については、土地改良区において速やかに補修等を行います。
これらの点検により、ため池の決壊等による災害の未然防止と農業用水の安定供給を図ってまいります。
配 布 資 料:・農業水利施設の取水前点検について [PDFファイル/126KB]
記者質問
遠隔教育配信センターついて
(記者)
難関大学を目指す生徒さんに向けて、こうした教育体制が立ち上がったことについて知事の受け止めは。
(佐藤知事)
どうしても難関大学を目指したいということで、大分市中心部の高校に進学したいお子さんがいます。今は全県1区になっていますけど、以前はそれぞれの地域の高校から、難関大学を目指して頑張るということもありました。
ただ、最近はそういう地域の高校で、難関大学を目指す生徒が相対的に少なくなってきていて、高校のあり方そのものを考えていかないといけないっていう話も出てきています。
特に数学や英語などは、習熟度のばらつきが大きくて、難しいことをやりたい生徒さんもいれば、ベーシックなことを勉強したい生徒さんもいます。そういう中で、レベルの高い授業を受けたいというニーズにも応えられるように、地元の中学校から近い高校に進学しても、そういう授業が受けられることになれば、長時間通学したり、下宿したりしなくてもすみます。それは生徒さんにとっても大きなメリットになります。もう一つは、地域にとっても高校はすごく重要な存在です。地域を元気にしてくれる存在でもあるので、そういう高校がちゃんと存続して、さらに地域の期待に応えられるような活動をしていくためにも、「自分が受けたい授業がしっかり受けられる」という体制を整えることには、大きな意義があると思って、これまで進めてきたところです。
企業誘致について
(記者)
半導体関連の電機・電子分野の件数が、昨年度から減っているが、問い合わせ件数や、半導体関連企業に関するアプローチの状況は。
(佐藤知事)
半導体については、企業名は公表していませんが、5件が立地しています。また、問い合わせも実はたくさん来ています。ただ、企業秘密の部分もありまして、詳しくは言えませんが、市町村にも話がきておりまして、比較的大規模な会社からの相談もあるとのことです。立地するにはやはり土地や、用水、電力といったインフラが大事ですし、交通インフラも重要です。例えばTSMCに近い中九州横断道路沿いとか、そういう立地がポイントになってくると思います。そういう意味では、半導体関連のニーズは引き続き高いと思っています。
それから昨年1年間を通して多かったと思うのが、電池関係、特に蓄電池の分野ですね。EVのニーズや動向が環境問題への対応とか、技術的に難しい部分もあるので、ちょっとスローダウンしているところもありますし、半導体については、米国の関税の影響がどうなるかなどの不確定要素もあって、今後を予測しにくい面もあります。ただ、中長期的に、10年スパンとかで考えると、間違いなく伸びていく分野だと思っています。だからこそ、用地やインフラの整備を早く進めて、しっかりと誘致できる体制を作っていくことが大事だと思っています。
(記者)
誘致に関する問い合わせ件数は。
(佐藤知事)
問い合わせ件数は開示できません。問い合わせは実感としては増えているといった状況です。
(記者)
半導体関連でいうと、どういうエリア、どういう内容のものが多いか。
(佐藤知事)
これもいろいろありまして、いわゆる半導体そのものというよりも、それを作るための素材とか装置関連とか、そういう周辺分野が多いです。前工程も後工程も両方あります。さらに、半導体関連ですが、具体的に内容がわからない問い合わせも多いです。例えば、「コンビナートの近くがいい」などの話もあります。参入企業が立地を検討する前に、商社や製造工程に関わる会社が先に来ることもあるため、そういうところが動き出して、あとで企業名がわかってくるパターンも多いです。
大きな土地を必要とする企業もあるようです。それが実現するかどうかは、大規模案件ほど世界中でいろんな適地を探しているでしょうから簡単ではないと思いますが、いくつかの候補地に入っているというのは間違いないと思います。
万博について
(記者)
大分ハローキティ空港として呼ばれるようになり、万博も始まったが、改めて県としての期待感と万博の来場者に大分県に来てもらうための課題は。
(佐藤知事)
大分ハローキティ空港と呼ぶことになったことで、やはり世界に向けた発信力が飛躍的に高まったと感じています。改めてサンリオのキャラクターは、本当に世界的に人気があるんですよね。サンリオエンターテイメントさんと連携して発信することができました。
それに加えて、5月には万博会場内で、日経地方創生フォーラムに私も登壇させていただき、小巻社長と対談し、大分県の魅力を発信する機会もあります。これらは、大分の魅力を世界に発信できる大きなチャンスだと思っています。
台湾に出張した時に現地の方々と意見交換をしましたが、大分には温泉以外に何があるのかという声が多く聞かれました。
こちらとしては一生懸命発信しているつもりでも、まだまだ伝わってないところがあります。例えば、ハーモニーランドを見るだけでも、その周りにはアフリカンサファリ、るるパーク(大分農業文化公園)、安心院のブドウ園がありますし、城島高原や別府ケーブルラクテンチもあります。さらに南に行けば、うみたまごや高崎山もありますし、さらに北には、宇佐神宮や国東半島に点在する六郷満山の寺院群もあります。
そうやって見ると、観光という意味で大分は本当に魅力がたくさんあるのですが、それがまだまだ知られていない。
昨年の福岡・大分デスティネーションキャンペーンでしっかり発信してきたつもりではあるんですけど、やっぱり海外で話すと、温泉以外に何があるのと聞かれることが多いんです。ですので、これからはますます発信をしっかりしていこうというところが一番の課題だと思っています。
人口推計について
(記者)
人口推計が発表されたが、大分県内で少子高齢化が進んでいるという結果についての受け止めは。
(佐藤知事)
これはもう全国的に進んでいる傾向ですけど、大分県の数字を見ても、全国で30位くらいでしょうか。減少率でいうと、年間1%ぐらいの減少になっています。分類で見ると、社会増減についてはプラスになったりマイナスになったりですが、外国人の増加も含めてわずかにマイナスです。自然増減の方は非常に大きなマイナスで、1万人以上の減少となっています。
日本全体のトレンドの中で、大分県もいろんな工夫をしていますが、まだトレンドを大きく変えるところまでは至っていないのが現状だと感じています。
引き続き「安心・元気・未来創造ビジョン2024」の中でも掲げているように、子育てしやすい社会づくりを進め、安心して暮らせる大分県づくりを目指して、さまざまな取組を総動員して、住んでもらえる、訪れてもらえる、移住してもらえる、そんな大分県を目指していきたいと考えています。
本日の午前中に部長会議でも話しましたが、婚活イベントなども工夫して、魅力のあるものにできないかと考えています。まだ決定したわけではなく、そういった議論があったということですが、例えばハーモニーランド、るるパークなど、県内のいろんな場所で婚活イベントを開催することで、出会いの場を提供しつつ、地域の魅力も発信していけたらと思います。
出会いが広がっていけば、それが将来的な人口増につながっていく可能性もあります。県としてもイベントを行いますし、市町村やテレビ局、団体の皆さんも協力いただいています。そうした活動を広げていって、子育ての大変さだけでなく楽しさや喜びといったメッセージも発信していきたいと思います。そういうことが、人口減少対策という意味だけではなく、どのように人生を過ごしていくかという大切なテーマの発信にもなり、大切だと考えています。
(記者)
今年は新しい長期総合計画の実行元年ということですが、特にこだわって取り組む人口増加につなげるための具体策は。
(佐藤知事)
いろいろありますが、インフラ面でいうと、住環境の整備が重要と考えています。例えば県営住宅ですが、3DKの間取りが一般的で、お子さんが1人なら何とかなるかもしれませんが、3人いるとか、男女の兄妹がいると、ちょっと手狭で子育てしにくいんです。
そこで、子育て世帯向けの県営住宅を整備したり、移住希望者向けにそうした住宅への支援策を広げたりして、より暮らしやすい環境づくりを進めています。我慢して狭いところで暮らすのではなく、のびのびと子育てができる環境を整えることで、定住促進にもつなげたいと考えています。
米国関税の影響について
(記者)
米国の関税について状況が目まぐるしく変わる中で、県経済への影響はどうか。
(佐藤知事)
状況がどんどん変わってきていて、難しいところなんですけども、まず、相談窓口を設けております。これは国でも設置していて、JETROでも対応していますが、大分県としても設置しています。ただ、今のところは、そんなに多くの相談が来ているわけではありません。
今すぐに影響が出ているわけではないですが、将来的に何か影響が出た時に、どういう支援があるのでしょうか、といった質問は多いです。
なかでも自動車への影響は心配されています。九州・大分北部の部品メーカーさんは、完成車メーカーに部品を納入して、それが米国に輸出されているケースが多いため、特に心配されています。
現時点で、すぐに影響があるという状況ではありませんが、影響が出てきた時には、それをしっかり把握して、いろんな取組をしていく必要があると思います。
大分県には自動車関連企業会という組織があるので、そこを通じて影響を把握する取組を進めています。
それから、米国にはお酒やお菓子、調味料、加工食品なんかも輸出されているんですが、2023年のデータで言うと、お酒と加工食品で2.73億円くらいですね。全体では10億円ぐらいの輸出額になっており、そのうちの27%が米国向けです。
これが今後、関税が20数%に上がる見込みなので、影響が出る可能性があります。その分、どこに販路を求めていくかということになります。
養殖ブリやおおいた和牛、あと製材品も輸出が多いです。例えば、養殖ブリは2023年で3.33億円、おおいた和牛は1.85億円、製材品は0.46億円、その他あわせて3,000万円ぐらいありまして、農林水産物全体で48億円ほどあります。
養殖ブリはこれまで無税だったんですけど、今後は10%の関税がかかる見込みです。牛肉は、もともと26.4%に10%の関税が加わり36.4%になってしまうため、大きな影響があります。
製材品については今のところ無税ですが、これも今後どうなるか分かりません。カナダとの関係もあって、木材を止めると、米国内で住宅の建築が鈍ることになるので難しいんじゃないかと思います。
牛肉も関税を引き上げると影響が大きいので、今後どうなるかという状況です。養殖ブリについても、米国ではブリを養殖する文化がないので、輸入せざるを得ない状況なのではないかと思っています。他の魚種に移っていくかもしれないので影響もまだ見えてない部分が多いです。
制度も次々に変わっていくので、状況を注視していく必要があります。
原発の処理水の問題で中国へのクロマグロの輸出が止まったときには、アメリカ向けに切り替えた事例もありますし、いろんな工夫をしていかなければなりません。県としても、しっかり状況を見ながら、必要な対応をしていくことになると思います。
(記者)
必要な対応として、県独自で補正予算を組んで支援するのか、あるいは国などに対応を求めていくのか。
(佐藤知事)
まだ具体的に大きな影響が出ていないので、今の時点での判断は難しいですが、もし影響が大きくなってきた場合には、リーマンショックやコロナのときと同じような対応が求められるかもしれません。
当時、一番効果的だったのは金融支援策でした。たとえば、信用保証協会の保証料がゼロになる、ゼロに近い金利になる、というような措置です。そういった対策が必要になってくるかもしれません。
あわせて販路をどう広げるかという話もあります。たとえば、台湾にはこれまで養殖ブリをあまり輸出していませんでしたけど、去年台湾に持って行ったところ非常に好評だったので、販路を広げる可能性はあると思います。
そういう販路開拓のお手伝いをさらに進めていくなど、いろんな対応が考えられますが、やはり影響の出方を見ながら、必要なタイミングでその都度判断していきながら、国にも、必要に応じて要請していくという形になると思います。
(記者)
自動車関連企業会を通じて影響を把握するという点について、既に調査を始めているか。
(佐藤知事)
順次始めています。やはり一番心配なのは部品メーカーになります。
たとえば、ダイハツ九州さんは主に国内市場向けですが、部品メーカーが作った部品が福岡県の日産やトヨタなどの工場に納入されて、それが米国に輸出される流れがあります。そのあたりの影響がどんなふうに出てくるかが気になります。
また、米国政府が生産拠点を米国に移したらむしろ支援を行うということが報じられていますが、そうなってくると、部品メーカーが一緒に米国に行くのか、それとも部品だけ輸出するのか、あるいは現地調達になるのか、それによっても大きく変わってくると思います。そうした動きも含めて、1つひとつしっかり状況を把握しながら、金融措置など必要があれば柔軟に対応していくことになると思います。
(記者)
トランプ大統領の今回の一連の行動、やり方についてどう感じるか。
(佐藤知事)
今まであまりなかった対応ですね。ただ、1980年代の日米貿易摩擦の際には、アメリカの赤字の大部分が日本との関係で生じていたということで、日米構造協議ですとか、リビジョニストという、アメリカの学者たちが日本の研究をたくさんしまして、日本はアメリカと違って異質だとして、これは止めなきゃいけないという、いわゆる日本バッシングのような動きが出ていました。自動車や半導体、電気製品など、あらゆる分野で高い関税をかけ、輸入制限するような議論が多かったんです。
それも、自由貿易の制限を関税でやるのではなくて、自主輸出規制で行えというのと、加えて、アメリカ製品を日本企業が買ってくださいということで、研究開発用の機器なんかで日本が必要なもののリストを作って、「この中からアメリカで作っているものをこれだけ買ってください」とリクエストがあったりしました。その結果、後に総理になった橋本龍太郎さんが通産大臣だった頃、自動車の輸出は185万台に制限されて、半導体は何%以上入れないという制限がかかるような、実質的な自主規制が行われました。
その時と少し形は違いますが、似ている部分もあると思います。ただ、その当時は、ターゲットが日本だけでしたが、今回は全世界を相手にしているので、そこは大きく違うところです。
当時、日本の自動車メーカーは自主規制しながら、生産拠点をアメリカに移していきました。今では、日本の企業がアメリカの自動車産業を下支えしているくらい、大きな存在になっています。一方で、日本から輸出する車は自主規制して台数は減りましたが、1台あたりの価格が上がり、とくに中古車の値段がすごく上がりました。新車の価格はGMやフォードと大きく変わらないくらいでも、3年落ちなどの中古車になったときの価格は、日本車のほうがグッと上がりました。それだけ日本車の品質を米国の消費者はわかっていたんだと思います。そういう消費者の反応もあり、メーカー側も185万台の自主規制をしつつ、うまく乗り切り、直接投資も含めてアメリカ市場を拡大していきました。
ただ半導体はその逆で、摩擦の影響を受けて投資が縮小して、サムスンとか台湾、中国にどんどんシェアをとられ、CPUの部分でもインテルやAMDに押され、それまで世界一だったNECや日立、東芝なんかもどんどんシェアを失っていきました。特に大分などの東芝のDRAM(ディーラム)工場は世界一だったのに、そういう経緯で低迷していきました。
当時は日米間の話しでしたが、今回は世界を相手にWTOのルールとはかけ離れた世界で、取引として行われているというのは、今までにあまりない状況でして、正直かなり違和感がありますが、それが現実としてあるなら、どう対処していくかということを考えなければいけないと思います。
ホーバークラフトについて
(記者)
万博が開幕し、大分ハローキティ空港の名称も使われるようになり、ホーバークラフトの空港ルート就航への期待は高まっているが、定期就航への進捗等の受けとめは。
(佐藤知事)
別府湾周遊は3,400~3,500人くらいの多くの方に乗っていただいていますし、それ自身が魅力の1つとして発信もできていると思います。
ただ、空港へのアクセスを改善するための定期就航を目標に、いろんなことが進められてきましたので、そういう意味ではできるだけ早いタイミングで就航できるといいなと思っています。
トイレ整備の問題もありますし、それから就航する上でやはり安全がしっかり、最終的に確認がとれるというのは、九州運輸局の認可が必要な仕組みとなっていますので、やはり安全は何より大事でありますから、安全の確保をしたうえで就航してもらいたいと思います。今の時点でいつからという見通しは立てられていないようですが、魅力の発信という意味で定期就航は早くできると良いと思っております。
(記者)
トイレ設置について大きな課題とおっしゃられていましたが、知事としては、トイレを設置したほうがいいと考えられているのか、あるいは設置せずに急ぐという考え方でいらっしゃるのか。
(佐藤知事)
常設のものまでは必要かどうか分かりませんが、非常時の対応を考えれば、何らかのものがあっても良いかとも思います。将来的に、もう少し長距離の観光周遊を行うなど、そういった利用法も出てくる場合にはトイレが必要になってくるのではないかと思います。
いずれにしても、さまざまな考え方があると思います。
(記者)
トイレを設置する場合と設置しない場合それぞれの就航予定時期は。
(佐藤知事)
簡易トイレを置くだけでいいのか、かっちりと船に組み込むようなトイレじゃないといけないのか、そういう構造上の問題も安全性に直結してきますので、やはり、九州運輸局の判断も含めて取り組んでいかないといけないと思います。どういう形式になるかによって時間は随分変わると思いますので、今のところ見通しは立っていないというのが現状であります。
任期折り返しについて
(記者)
知事も任期の折り返しが近づいているということで、これまでの2年間を振り返り、知事ご自身の評価や思いは。
(佐藤知事)
この2年間は、いろいろな課題を設定して取り組んできました。ただ、課題の設定というのは私個人のものではなく、県全体の課題であるべきだと考えています。
「安心・元気・未来創造ビジョン2024」という10年の長期総合計画を軸にして、そこから環境、商工、農業、こども・子育てといった各分野での個別の課題設定がなされてきています。そうした課題に対しては、できるだけ県民の皆さんに発信しながら、意見をいただきつつ進めてきたつもりです。
ただ、自分で自分を評価するのは難しいですし、評価は県民の皆さんにお任せしたいと思っています。
着任当初から取り組みたいと思っていた遠隔教育配信センターもスタートしましたし、来年4月には夜間中学も開校します。大分ハローキティ空港は、準備期間がわずか3か月ほどだったにも関わらず、県庁の職員や大分航空ターミナル株式会社の皆さんが一丸となって、短期間で実現してくれました。サンリオエンターテインメントの小巻社長のリーダーシップがなければ、このスピード感は難しかったと思います。昨年の福岡・大分デスティネーションキャンペーンも成果が出ましたし、それを引き継いで取り組んでいただいています。
一方で、人口減少のように、すぐに成果が見えにくい分野もあります。企業誘致なんかもそうですが、長いスパンで取り組まないといけないテーマもあると思います。企業誘致も時間がかかります。
評価は、県民の皆さんにお任せしたいと思います。
(記者)
評価は県民の皆さんにお任せするということでしたが、あえて100点満点でどれくらいの自己採点をつけるか。また残りの任期2年間、どんなふうに取り組んでいきたいとお考えか。
(佐藤知事)
自分で点数をつけるのはやはり難しいですね。
「安心・元気・未来創造ビジョン2024」ができましたので、それを少しでも前に進めていく、実現に向けた道筋をつけていく2年間にしたいと思っています。
このビジョンは10年計画ですが、5年で見直しますし、さらにその先の将来も見据えたものです。10年で完了しないものも多いので、無理して結果を急がず、将来のために一歩一歩確実に進めることが大事だと思います。
たとえば「豊予海峡ルート」なども時間はかかりますが、着任当初よりもだいぶ進んできているという実感があります。ただ、逆にどこかで止まってしまえば、おそらく未来永劫できないとも思いますので、着実に道筋をつけていきたいと思っています。




