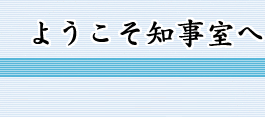
令和7年5月7日知事定例会見
動画はYouTube「おんせん県おおいた公式」へ
日時:令和7年5月7日(水曜日)13時30分~
場所:第一応接室
記者会見時に配布した資料を掲載します。

まちなかアートフェスタについて
県内各地で、芸術を楽しんでいただくための「まちなかアートフェスタ」を、5月17日から順次開催します。
昨年も行いましたが、第2回目となる今年は、別府アルゲリッチ音楽祭が25回目を迎えることを記念して、5月17日に大分市中心部で、おおいたクラシックフェスティバルを開催し、街をクラシック音楽で彩ります。
メイン会場の大分駅前広場では、県内はもとより、海外からも演奏家をお招きし、演奏を披露していただきます。そのほか、5月14日に東京オペラシティで開催する別府アルゲリッチ音楽祭・東京公演でのマルタ・アルゲリッチさんの演奏を、フィルムコンサートとしてお届けします。あわせて、俳優の石黒賢さんにトークゲストとしてお越しいただく予定です。
また、セントポルタ中央町商店街やガレリア竹町ドーム広場、大分県立美術館にもステージを設け、一般公募により選ばれたお子様から大人の方まで、県民の皆様に演奏を披露していただく機会も設けておりますので、お気軽にお出かけいただければと思います。
さらに、5月19日には、「大分ハローキティ空港」においてコンサートを開催し、中ヒデヒトさん(クラリネット)、宮崎陽子さん(ピアノ)にご出演いただきます。7月26日には、「さんふらわあ」の船内において、武内麻美さん(ヴァイオリン)、後藤秀樹さん(ピアノ)による演奏をお届けします。そして、10月から開催される「国東半島芸術文化祭」の期間中にも、関連イベントを実施する予定ですので、ぜひこれらの機会を捉え、クラシック音楽に触れていただければと思います。
配 布 資 料:おおいたクラシック・フェスティバル チラシ [PDFファイル/1.71MB]
第20回大分県障がい者スポーツ大会について
第20回大分県障がい者スポーツ大会を開催いたします。本大会は、障がい者スポーツの普及と、障がいのある方々への理解を深めること、何より、障がいのある方々が活躍できる場を創出することを目的としており、今回で20回目の開催となります。また、10月に滋賀県で開催されます第24回全国障害者スポーツ大会への県派遣選手の選考会も兼ねています。
4月6日には既にアーチェリー競技が開始されており、今月24日のボウリング競技まで、個人種目が7競技ございます。延べ約1,200名の選手の方々が参加します。
私も5月17日には、クラサスドーム大分で開催する陸上競技とフライングディスクの合同開会式に出席する予定です。
当日は、11月に日本で初めて開催される東京2025デフリンピックのPRブースを設置するほか、障がいのある方が制作した雑貨の販売、キッチンカーの出店などもございますので、ぜひこの機会に会場へ足をお運びいただきまして、目標に向かって全力を尽くす選手たちへの温かいご声援をお願いします。
常々感じることですが、車椅子バスケットボールや車椅子テニスなど、障がいのある方々がアスリートとして、健常者以上に卓越したパフォーマンスを発揮されることがあります。皆様にも、障がい者スポーツの魅力を、この機会に体験していただければと考えております。
配 布 資 料:第20回大分県障がい者スポーツ大会 概要 [PDFファイル/252KB]
臼杵港新フェリーターミナルおよび大分港大在西RORO船ターミナルの供用開始について
まず、臼杵港のフェリーターミナルですが、本年3月に完成した新たなバースが5月17日から供用開始となります。
これによりまして、港湾の対応能力が向上し、船舶の混雑が緩和され、危険な状況も改善される見込みです。今回のフェリーターミナルの整備・移転により安全な航行が可能となります。
また、耐震性の高い岸壁と、背後には緑地を整備することで、災害発生時の緊急物資の輸送拠点、そして平常時には地域の皆様の憩いの場としてご活用いただくことを予定しております。
5月17日から新フェリーターミナルへの移転を実施いたしますので、運送事業者の皆様におかれましては、お間違えのないようお願い申し上げます。
次に、大分港大在西RORO船ターミナルについてですが、現在、物流拠点として清水港に週3便、東京港に週4便のRORO船が運航しております。令和5年には、3万240台を超えるシャーシが取り扱われ、大変重要な物流の役割を担っております。
しかしながら、RORO船が出港しておりました場所の水深が7.5メートルしかないため、これまでより大きな船舶が接岸できるよう、水深9メートルの岸壁を有する新たなターミナルを建設しました。将来的には更なる需要の増加が見込まれるため、2バース目を整備することも視野に入れておりますが、まず1バース目が完成し、5月24日から供用を開始する予定です。
今回の整備により、より大型の船舶にも対応できるようになり、輸送効率の向上が図られます。また、岸壁背後の用地は、従来の埠頭用地と比較して2.4倍の広さとなり、後背地も活用できます。シャーシ置き場においては、DX技術を活用し、受付の無人化や駐車位置のシステム管理を行い、荷役作業の効率化も合わせて実現しました。
今後は大型船の入港に対応できるようになりますし、RORO船ターミナルから宮河内ICまでは近距離であり、そこから東九州自動車道、そして現在建設を急いでおります中九州横断道路へのアクセスもよいことから、九州の東側の物流拠点として、さらに活用されるものと期待しております。
このような港湾の整備は、本県にとって大変重要であり、国土交通省にも様々な要望活動を行っておりますが、今後も計画的に事業を推進し、九州の東の玄関口として、利用者の皆様に選ばれる港となるよう、港湾の整備に取り組んでいく所存です。
配 布 資 料:フェリーターミナル・RORO船ターミナル概要 [PDFファイル/687KB]
婚活イベント等の実施について
本県では、婚活支援の取組として、3つの事業を実施しております。
まず1点目は、婚活イベントです。
今年で3回目となりますが、5月18日に知事公舎において、ガーデンスイーツパーティーを開催いたします。
本イベントは、これまで2回開催し、63名の方にご参加いただき、10組のカップルが誕生しました。今回は、男女各20名、計40名の参加者を5月12日正午まで募集しておりますので、県のホームページ等からご応募いただければと思います。
2点目は、新規入会応援キャンペーンです。
県の出会いサポートセンターでは、昨年好評いただいた新規入会キャンペーン、登録用写真の無料撮影サービスを、今年も5月から実施します。現在1,400名いる会員の更なる増加の後押しにもなるものと考えています。
3点目は、令和7年度婚活支援者等ネットワーク情報交換会を開催です。
これは、県や市町村、商工団体、民間事業者の方々などとともに、婚活支援者等のネットワークを構築するための情報交換会を開催し、各地域でのイベント情報の共有など婚活支援の更なる活性化を図るための取り組みです。
当日は、今年2月に、OITAえんむす部部長に任命した荒木直美さんに、最新の婚活事情についてお話いただき、グループごとに意見交換やワークショップを行い、婚活支援の機運醸成を図ります。
少子化について、本県における出生数は現在6千人台となり、最も多かった時期の4万2千人程度と比較しますと、約7分の1程度にまで減少しております。その大きな要因の一つとして、未婚化、晩婚化が進み、成婚に至る件数が減少していることが挙げられます。
結婚されたご夫婦の出生数は比較的安定しておりますが、婚姻件数の減少が深刻な状況です。
このような状況を踏まえ、例えば、物価と賃金の好循環による賃金上昇といった対策はもとより、子育て支援による負担軽減も重要であり、並行して、出会いの場を積極的に創出し、結婚を希望されながらも機会に恵まれない方々を後押ししていく取り組みを、今後も強化したいと考えております。
配 布 資 料:新・おおいた出会いイベント縁結びin知事公舎 [PDFファイル/401KB]
新規入会応援キャンペーン!!写真館で無料撮影 [PDFファイル/1.01MB]
令和7年度婚活支援者等ネットワーク情報交換会 [PDFファイル/396KB]
旧優生保護法補償金等支給対象者への個別通知に係る調査状況について
本県では、昨年10月の法の成立を受け、大分県が個人情報を把握しておりました101人の方につきまして、市町村の協力を得ながら、住民票や戸籍等により、所在確認調査を実施してまいりました。
生存者がいらっしゃることは既に公表させていただきましたが、101人のうち、現在までに生存が確認できた方が3人、死亡が確認された方が49人となった一方で、所在が確認できておらず、引き続き調査を行っている方が49人います。
生存が確認できた方に対しては、既に補償金に関する個別通知を実施済みです。また、死亡が確認された方につきましては、今後、補償対象となりますご遺族への個別通知を行っていく予定です。
このご遺族への個別通知を適正かつ円滑に遂行するため、大分県弁護士会が業務支援にご協力いただけることとなりました。
弁護士会との連携は本県独自の取組であり、この後、担当部局と弁護士会が記者会見室にて記者説明を行わせていただきますので、ぜひご参加いただければと思います。
また、101人以外にも、支給対象となりうる方に対しましても、補償金等支給制度の情報が届くよう、様々な機会を捉えて積極的に周知・広報を行い、適切な補償を進めてまいります。
県の相談窓口もありますので、そちらのご活用もぜひお願い申し上げます。
配 布 資 料:旧優生保護法補償金等支給対象者への個別通知に係る調査状況について [PDFファイル/291KB]
記者質問
臼杵港新ターミナルビル及び大分港大在西RORO船ターミナルについて
(記者)
港の整備については、今後どういう課題が残っているとお考えか。
(佐藤知事)
まず大在西RORO船ターミナルでは、1バース目ができまして、その利用状況を見ながら2バース目をどのように整備していくか、検討を進めていくことになります。より多くの方々に1バース目を使っていただき、2バース目の拡張計画を進めていければと考えています。
大在西は物流用のターミナルでありますが、あわせて県内の旅客埠頭の整備も大変重要です。
例えば別府湾の中の整備も課題になってくると考えており、国土交通省の方には様々な要請をしています。さんふらわあをはじめ、旅客船が入ってきている港の拡充も課題として、取組を進めていくべきと考えているところです。
(記者)
大在西RORO船の説明の中で利用実績の報告があったが、細かい数字とそれは過去最高ということでよいか。
(佐藤知事)
平成27年がシャーシ数7,512台のところ、令和5年には3万240台になりましたので、約4倍に増えているということです。
(土木建築部審議監)
RORO船の取り扱いシャーシ台数(シャーシ:トラックに牽引されている後ろ側の台の部分)は、令和5年が3万240台と過去2番目の数値であり、令和元年が3万286台で過去最高でした。
(記者)
この結果はモーダルシフト等の影響や県の取組もあってのことか。
(佐藤知事)
物流のニーズはさらに高まっているので、大分港大在公共埠頭のところにはJAさんが冷蔵倉庫を造ったり、JXさんのリサイクルセンターもあります。
いずれも物流と関係のある施設が立てられていますし、こうした物流拠点に様々な産業が立地してきますので、やはり大在や坂ノ市、鶴崎が、大分県の中で人口が唯一増えている地域であることの裏返しです。
そういう意味では、もう1つの産業地域である、例えば中津港の整備なども課題になってきます。中津日田道路の整備と合わせて、整備していかないといけないと思います。
(記者)
このRORO船がきっかけで、大在公共埠頭がまた注目されるようになるか。
(佐藤知事)
今でもRORO船は非常にニーズが増えています。清水が中心でしたが、東京も便数が多くなっています。
これはつまるところ産業面が活発化しており、特に東京や清水からは、機械などが入ってきており、逆に、大在からは、農産物や、工業製品が、清水あるいは東京に運ばれているところです。
(記者)
別府湾について、さんふらわあの話もあったが、ターミナル部分の課題も含め、再編整備の進捗はいかがか。
(佐藤知事)
さまざまな国の事業や計画の中の一つとして行うような形もありますので、これからの話になります。いずれにしても、ニーズは非常に高くて、それを国土交通省にも説明をしながら、旅客についてもこれから取り組んでいかないといけないと思います。
旧優生保護法について
(記者)
弁護士と連携するというのは大分県が独自に行っているということですが、全国初ということになるか。
(佐藤知事)
知る限り全国初だと思います。定例会見終了後に弁護士会の方と共同会見させていただきますので、また改めて確認いただければと思います。
(記者)
弁護士の方々と協力することで、効果として期待されることは。
(佐藤知事)
旧優生保護法で被害を受けられた方々、補償の対象になる方々の支援の取組を最初から行ってきたのは弁護士会の方々です。もちろん県も協力しながら、共に取組んできておりましたが、専門家の方々と一緒になって取り組んでいくということは、被害の実態を踏まえた取組をする上でも、大変意義があると考えています。
(記者)
今回所在が確認できず、調査中の方が49人いたということであるが、所在が確認できていない理由は。
(佐藤知事)
これは戸籍や住所などを調べますが、わからないということです。
(福祉保健部審議監)
私どもの方で持っている資料等で、名前が一致しないとか、記載されている住所地にその方が見当たらないといったことなどで、確認できていないケースがあるというものです。
(記者)
調査状況についてですが、101人のうち少なくとも49人の方については既に亡くなっていたということについての知事としての受け止めは。
(佐藤知事)
長い期間のさまざまな行政の措置の結果としていうことでありますので、49人の方が結果的にお亡くなりになっていたということで、大変申し訳ないことだと思います。そういった方々に対しましても、親族の方々に対する補償という仕組みがありますので、そこをしっかりとやっていきたいと思います。
(記者)
亡くなられた49人の方々のうち、記録がわかった2018年からこれまでの間に亡くなった方がいるのか。また、存命中の救済ができなかったケースがあるかどうかということについて知事の受け止めは。
(佐藤知事)
もしそういうことがあるとすれば大変申し訳ないことだと思います。
(福祉保健部審議監)
人数など具体的な件数などについては、後ほど記者説明にてお答えさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
婚活イベントについて
(記者)
今回のイベントを知事公舎で行う意義や効果は。
(佐藤知事)
もう3回目の開催になりますが、1つは公舎ですので、できるだけさまざまなイベントに使ってもらいたいというのもありますし、もう1つは、知事公舎で行うイベントに行ってみたいなと興味を引く面もあると思いますし、もう1つは、参加された方々から知事公舎のような場所で行うイベントであれば安心なのでぜひ参加したいという声も聞きました。
そういう意味で婚活イベントの場としてふさわしいのではないかと考えています。ちなみに、今後、例えばホーバークラフトに乗りながら婚活イベントをしてもらうとか、そういうさまざまな場を設定して、楽しみながらイベントに参加してもらうということをやってもらえればと思っています。
ホーバークラフトについて
(記者)
空港へのアクセス、定期就航について現状を教えていただきたい。また、安全確保について、大体どれぐらいを目安に安全確認検査に入るべきだと事業主として検討されているか。
(佐藤知事)
事業主は、大分第一ホーバードライブだと思います。大分県は船主であり、それを傭船契約でお貸ししていますので、それを使って事業をしているのは大分第一ホーバードライブだと思います。
ただ、安全性の確保については、万全を期してもらいたいと従来から第一ホーバードライブに対して要請してきました。安全確認検査は、国土交通省、権限は九州運輸局長だと思いますが、そちらが安全性を確認することになっています。
今まで4,140人の方が別府湾周遊で乗船されていますが、お客様を乗せての事故は一度もありません。周遊では30分ぐらいで戻ってきていますので、そうした運航は、操縦士の方も、整備を担当するスタッフも含めて、しっかり対応ができるようになってきております。強風時などは運休したりしながら、安全面を重視した運航を行い、お客様が乗っている時には絶対に事故を起こさないという対応が今まではできています。
これからも安全を大前提にしていくと思いますが、定期就航は、定時性確保の点で、周遊に比べると、より厳密な運航を求められますので、そういったところの準備・整備が万全にできていく必要があります。
トイレ設置の問題もありました。特に非常時に、例えば途中でエンジンが止まって動かなくなった時にやはりトイレが必要でしょうといった議論もありえますので、そういった時どうするかも含めて、検討をさらに重ねて準備していると聞いております。
周遊はかなり定着してきているところもありますが、定期運航についてはいつまでと私から申し上げるような状況にはありません。
そういったところを検討しながら、しかるべき時期に、九州運輸局の検査に臨むというスケジュールになると思います。
個人献金について
(記者)
知事の個人献金の所在地欄に、企業や法人の所在地が記載されていたという報道で、知事ご自身や後援会の方でどのように把握しているか。また実際に、企業法人の所在地が記載されていたということについて受け止めは。
(佐藤知事)
後援会事務局に確認したところ、献金、あるいは会費という形でいただく時は、個人の名前と、個人のお住まいの住所にしてくださいということは何回も繰り返しお願いしていたということです。けれども、結果として4名の方が、自宅ではない事業所の住所を書いていたようです。
政治資金規正法では、同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものについては、寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日などを報告書に書かないといけませんとなっています。総務省の見解では、個人献金の住所は、実態に即して記載する必要があるというものです。ですので、個人の住所というよりは、実態に即して記載する必要があるということで自宅とは書いておりません。
ただ、一番大事なことは、会社からの企業献金をあたかも個人献金のように寄附しているということはあってはいけないことで、これは政治資金規正法で罰則がかかります。
そのようなことはないと確認できています。ただ、実態に即して記載する時に、その人が家でなくて、そこの会社に寝泊まりしているような場合でも、自宅じゃないということで指摘されることはあるかと思います。
自宅の住所を記載しますと、名前と住所がインターネット上に全部出るわけですね。そうすると自宅に献金をしてほしいとか、場合によっては、この人に献金するのはおかしいんじゃないかという抗議があったりなどの防犯上の理由等で、個人の住所を書くのは避けたいという人がいるそうです。合わせて、ほとんど自社に寝泊まりしているような方々が会社の住所を書いて、確定申告時の書類の送り先を会社にしてもらった方が便利も良いということもありました。そうした理由などもあって、4名の方が自宅以外を記載していました。
したがって、受け止めとしては法律違反ではないということです。後援会の方では、一人ひとりの記載の住所が、本当に自宅かどうかを自宅まで行ってチェックすることはできないんですけども、自宅の住所を書いてくださいと何回も要請はしてきています。ただ、その結果、自宅住所を書いていなかった方が4人いらっしゃったということです。
企業献金にあたるかどうかの判断のポイントとして、やはり個人の住所を書くというのは基本的に大事なことだと思っています。ですので、今後もその点はしっかりお願いしていく必要があると考えています。もちろん、献金していただけるのは本当にありがたいことなんですけど、その際にはしっかりとお願いしていくということですね。
ただ一方で、法律の観点からどう考えるかというと、最近ではいろんな人が自宅まで来たりして、防犯上の問題もありますし、個人名と住所がすべてインターネット上に出てしまうということが本当に良いのかどうか。そういった点についても、やはり一度しっかり検討する必要があるんじゃないかとも思っています。
(記者)
改めて、あくまでも個人の方が献金されていたということなんですけれども、どういうふうに呼びかけをしていきたいか。
(佐藤知事)
個人献金に関しては、その住所も実態に即したものを記載する必要があるというのが、今の総務省の見解から読み取れると思います。つまり、個人の住所を書いてくださいということです。ですので、今後も「自宅の住所を書いてください」と伝えることを徹底していく必要があると思っています。
もし今後、また献金していただけるという場合には、しっかりと徹底していかないといけないと思っています。
ただ一方で、ちょっと難しい問題でもあり、いろいろなところで議論がされているという話は聞いています。例えば、住所は全てじゃなくて、大分県大分市まで書けば良いのではないかなど、そういう意見もあります。しかし、それだと逆に「実態に即して記載する」という観点からすると、ちょっと難しい面もあるんじゃないかという感じもします。
そのあたりは、問題意識としては、総務省や関係する皆さんの間でも広く共有されているようです。
また、繰り返しになりますが、企業献金というのは禁止されていますし、それに違反すると罰則まであるわけですので、そこは絶対にあってはならないと思います。
(記者)
個人情報をネットに公開されるため、防犯上の理由で避けたいという人がいるという話は、該当の4人の皆様はそういう話があるのか。
(佐藤知事)
4人にそれぞれ改めて確認はしていませんが、ちょっと額の大きな方に聞いてみるとそういうことでした。実は4人のうち2人はちょうど5万円の献金なので、そもそも収支報告書への記載は義務付けられておりません。
(記者)
これまでも呼びかけで要請していたとあったが、法人や団体の所在地として報告されている方がいるという認識はあり、ある程度呼びかけはしている中で、それが叶っていないとの認識か。
(佐藤知事)
後援会事務所に確認していませんが、コンプライアンス上、総務省の見解を見ると、個人の自宅住所だろうということでありますので、献金のお話があるたび、あるいは書類を書いてもらう時に、個人の住宅住所をお願いしますと言っていたということです。今回こういう形で、問題であるという指摘があったわけですので、一層そこは徹底をしていきたいということです。
(記者)
より一層徹底していくという言葉もありましたが、要請方法を変えるなど考えはあるか。
(佐藤知事)
要請をさらに増やしていくしかないと思います。毎回、本当に住所かどうかを確認するところまでは実務上無理と思いますので、さらに機会をとらえて要請するという対応にならざるをえないのかなと思います。
(記者)
政治資金の専門家からは、住所記載は個人献金であることを担保する重要な情報であって、企業や団体所在地を記載されれば、事実上の企業・団体献金が疑われる、という指摘もあるが改めて知事の見解は。
(佐藤知事)
そういう指摘もあると思いますが、やはり実態に即して記載する必要があると総務省の見解が示されていますので、例えば企業内に別室があって、社長さんがそこで寝泊まりしていれば、住民票上の自宅は別にあっても、会社の住所を実態に即して書いてもらうのは、おそらく総務省の見解に反してないと思います。
ですので、企業の住所を書いたらそれで疑われるというのは議論があると思います。ただ、どうやって企業献金を防いでいくのかは難しいですね。確定申告の税務書類とか見るとわかるかもしれませんが。専門の先生のおっしゃることもよくわかりますし、大変難しい課題だと思います。
(記者)
他県のケースで、団体の役員や社員がいっせいに個人献金をしていて、事実上の企業献金の疑いがあるという報道もあったが、今回の調査の流れで企業献金でないことが確認できる手法はあるのか。また、個人の住所地がオープンになる問題点は、何らか国などに制度変更を求める意図も含められているか。
(佐藤知事)
まず、最初の点は、私も5万円を超える人を確認したところ、そういう亊例ではなかったことを確認できました。要するに一人ひとり、全部住所などが違うので、まとめてということはないと確認できています。
それから、後者では令和8年分の収支報告書から制度が変えられるという話をちょっと聞いています。すべての番地まで書かないでいいような形になっているというふうに聞きましたけど、逆に、それで企業献金の可能性をどうやって排除するのか私もよくわかりませんけど、さらに必要があれば、そういう制度見直しについても検討してもらいたいと思います。
(総務部長)
令和9年1月以降に公表する収支報告書から、そうした配慮を含めた制度改正が予定されているので詳細はまた取材していただければと思います。令和9年1月以降に公表する報告書からは、少し見直すかもしれない話であり、過去の分はまた別でございます。
(佐藤知事)
そういう意味では本当に大変な難しい問題をはらんでいると思います。
(記者)
他県では、寄附者の企業が、県発注工事を落札したり、随意契約を結んだりしていた例もあったということだが、佐藤知事の個人献金の供与者に関してはそうした事例はあるか。
(佐藤知事)
ないと思います。献金者は基本的に個人ですから、ないはずです。また、例えば入札などは健全性を確保した上でやっています。
ガソリン税について
(記者)
ガソリンの暫定税率の廃止について、政府の試算では大分県は52億円の減収見込みと出ていましたが、知事のお考えは。
(佐藤知事)
制度は、国が決めることですから、それに対応していろんな処理をしていかないといけません。
大分県では、1年間で50億円ぐらい減収になるというふうに想定されますが、今後、制度等の詳細が検討されて、それによって影響額も変わってきますので、それに対応した措置が必要になってくるかもしれません。
いずれにしても、国で税制について議論するときは地方財政の影響も含めて検討してもらいたいと思っています。




