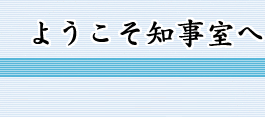
令和7年5月20日知事定例会見
動画はYouTube「おんせん県おおいた公式」へ
日時:令和7年5月20日(火曜日)13時30分~
場所:第一応接室
記者会見時に配布した資料を掲載します。

婚活イベントについて
5月18日に知事公舎で開催した婚活イベントには、40名の方にご参加いただき、7組のカップルが誕生しました。取材いただき、ありがとうございました。
ご存じのとおり、大分県で1年間に生まれてくるお子さんは6,000人強となっており、ご成婚される方も毎年3,500組ほどになっています。結婚される方が増えるということは、人口問題の観点からも重要ですし、なにより素敵な出会いを求めて婚活に臨む方が多くいらっしゃいます。今後も、そうした出会いの場を継続的に提供できるよう、取組を進めてまいります。
次回は6月28日にホーバークラフトやホーバーターミナルを利用して開催する予定です。会場の都合上、今回は男女各15名、合計30名の募集となっております。募集は6月20日までですので、多くの方からのご応募をお待ちしています。今回も素敵な出会いが生まれることを期待しております。
また、県では今後も、振興局ごとに婚活イベントを継続的に実施していきたいと考えておりますので、引き続きお願いします。
配 布 資 料:新・おおいた出会いイベント縁結びin大分市 チラシ [PDFファイル/230KB]
梅雨時期の洪水や土砂災害等に対する備えについて
まもなく梅雨を迎えます。この時期は、毎年のように全国各地で豪雨災害が発生しています。
昨年の台風第10号による大雨では、国東半島を中心とした県内各所において、河川の氾濫、土砂崩れなど、甚大な被害が発生しました。
こうした被害を防ぐためには、事前の備えが非常に重要です。
そのため、全国的に5月は水防月間、6月は土砂災害防止月間とし、この時期に県内で点検などを集中的に行っています。
まず、河川については、県が管理する河川のうち、堤防のある153河川、総延長377kmの範囲で点検を実施し、今月末までに必要な補修を行います。
また、避難所や病院、老人ホームなどの要配慮者の利用施設が立地する土砂災害警戒区域と山地災害危険地区の計272か所についても点検を行い、その結果は、地域の皆様に日頃の備えとして活用していただけるよう、市町村を通じて回覧等で周知します。
さらに、危険箇所のパトロールについては、5月16日から6月15日までの1か月間を防災体制整備促進月間と定め、市町村と連携して、特に警戒が必要な箇所をピックアップし、災害時の現地での対応の確認を進めます。
次に、梅雨時期に備えた啓発活動についてですが、5月20日からテレビCM、新聞、ラジオ、県の広報誌などを通じて注意喚起を行います。
加えて、6月1日には、ハーモニーランドにて「砂防フェスタ」を開催します。砂防の模型体験や防災クイズなどを通じて、親子で土砂災害に対する備えについて学べる内容となっています。昨年12月に県とサンリオ、サンリオエンターテイメントとの間で協定を締結しており、その取組の一環として行うもので、ハーモニーランドに特設ブースを設けて開催しますので、ぜひお立ち寄りください。
続いて、6月2日は「県民防災アクションデー」となっており、県内14市町村でサイレンが鳴る訓練を行います。サイレンが聞こえるかどうか確認いただくとともに、備蓄品や避難場所などの確認もお願いしたいと思います。
また、大分県の「安心・元気・未来創造ビジョン2024」推進委員会において、外国人観光客への防災情報が伝わりにくいという課題などを提言いただきました。これを踏まえ、外国人観光客向けの多言語防災リーフレットを作成し、空港や観光案内所などで配布するほか、県のホームページからもダウンロードできますので、インバウンドのお客様の多いホテルなどの施設では、自由にダウンロードしてご活用いただければと思います。
最後に、災害時の3つのお願いについてです。
災害時に「人的被害ゼロ」にするためには、一人ひとりの「自分の命は自分で守る」という意識と実際の行動が欠かせません。
そこで、県民の皆さんには、「備蓄」「早めの避難」「声かけ」の3つの行動をお願いします。
まずは、しっかり備蓄です。
家庭で必要な水・食料・生活用品を最低3日分、可能であれば1週間分の備蓄をお願いします。
5月26日および27日には、県庁舎本館1階のATM周辺で非常持出品や備蓄品の展示を行うほか、非常食の無料配布も実施する予定ですので、ぜひご来場ください。
2つ目は、早めの避難です。早めの避難が命を守る鍵となります。
雨の多いこれからの時期、家の周囲で濁った湧水が出たり、ひび割れが見られたり、普段とは違う音が聞こえたりした場合には、避難指示を待たずに、ただちに安全な場所へ避難し、地域の消防団などに連絡を取っていただければと思います。
3つ目は、みんなに声かけです。
まず自分の安全を確保したうえで、家族や近隣の方々への声かけを行い、いざという時に支えあう行動をしていただきたいと思います。
このように「備蓄」「早めの避難」「声かけ」を実践いただき、県民の皆さんと一緒になって、今年も災害時の人的被害ゼロを目指していきたいと考えております。
配 布 資 料:梅雨時期の洪水や土砂災害に対する備えについて [PDFファイル/161KB]
災害時の多言語情報リーフレット [PDFファイル/861KB]
令和6年度県外からの移住状況について
令和6年度の移住者数は、5年度の1,714人を上回る1,746人となり、5年連続で過去最多を更新しています。移住者数が1,000人を超えるのはこれで8年連続になります。
これは、これまで移住希望者のニーズに応じたきめ細かな支援を、市町村とも連携して実施してきた結果と考えています。
移住者を年代別に見ると、30歳代、10歳未満、20歳代が多く、若い世代の比率が高くなっています。また、移住前の住所地では、九州・沖縄や首都圏が多くなっています。
先月、国が公表した人口推計では、国全体で少子高齢化の人口構造となっており、当分の間、大幅な自然減は避けられないものと考えます。大分県では年間およそ6,000人が生まれ、1万6000人が亡くなっていますので、年間で約1万人の自然減となっています。一方、社会増減は、年によってプラスになったりマイナスになったりしています。
私も、県内各地を訪れる「県政ふれあい対話」の場などで、県外から移住されてきた方々と話す機会が多いのですが、そうした方々が地域に溶け込みながら、新しい活力をもたらしてくれていると実感しています。
そういった意味でも、市町村と連携しながら、今後も移住支援策をさらに進めていきたいと考えています。
続いて、具体的な移住支援策についてお伝えします。
まず、「移住支援金」についてですが、これは東京圏から移住された方を対象に、国の制度として、一世帯当たり100万円を支給するものです。本県では、それに加えて独自支援策として、東京圏以外からの移住者も支給対象としており、これに、子育て世帯には、こども1人当たり30万円を加算していましたが、今年の10月からはこれを50万円に引き上げ、より手厚い支援にしていきます。
また、若者の移住には、就業支援が欠かせません。これまで、移住者のITスキル等の習得を支援してきましたが、本年度からは、新たに女性や県内企業に需要の高いファイナンシャルプランナーの資格取得支援を追加し、6月上旬から募集を開始します。
このほかにも、県内外やオンラインで相談窓口を設置しているほか、各種移住相談会も随時開催しています。
関東や関西などにお住まいのご家族・ご親戚、あるいは縁故のない方でも、移住を検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひこれらの制度をご活用いただければと思います。
配 布 資 料:令和6年度 県外からの移住状況 [PDFファイル/348KB]
令和6年度農林水産業への新規就業者・企業参入の状況について
まず、新規就業者数ですが、令和6年度は農林水産業の合計で472人となりました。これは調査を始めた平成16年以降、過去最多の数字です。
就農学校やファーマーズスクール、林業アカデミー、漁業学校などの研修体制の整備、そして研修生への細やかな支援などが、新規就業につながっていると考えられます。
内訳としては、約4割の191人が雇用型、つまり企業などに雇われて働く形態での就業者となっており、女性の新規就業者も95人と過去最多となるなど、一定の成果が見られています。
今後も、農林水産業をやりがいのある魅力的な産業として発信しつつ、就業相談会や就業体験の機会提供、女性・子育て世代への支援などに力を入れていきます。
続いて、農業への企業参入についてです。
令和6年度は21件の参入があり、10年連続で20件以上を達成し、平成19年からの累計では400件となっています。
これらの企業の目標産出額は19億3千万円、また新規雇用者数は176人が計画されています。
参入企業の一覧もお配りしていますが、上から3番目の「株式会社ファーマインド大分農園」という企業は、青果物の輸入・加工・流通・販売を手がける大手企業で、国東市に大きな農園を開設し、梨18ヘクタール、さらにかんしょ20ヘクタールの大規模生産に取り組む予定です。
昨年策定した農林水産業振興計画においても、地域を牽引する中核的な経営体の育成に重点的に取り組む方針としていますので、今年度からは農林水産部内に「企業参入・支援室」を新設し、さらに取組を強化していきます。
地域の産地づくりや雇用の創出、より影響力のある企業の参入促進により、農業の成長産業化を進めていきます。
配 布 資 料:令和6年度 農林水産業の新規就業者の状況 [PDFファイル/51KB]
令和6年度 農業への参入企業 [PDFファイル/104KB]
第1回大分県観光振興財源検討会議の開催について
昨年度、大分県観光の更なる発展に向けた有識者会議において、今後増加が見込まれる新たな観光需要に対応する中長期的な財源として、宿泊税などの特定財源の検討について提言いただきました。
これを受け、今年度からスタートする「第5期ツーリズム戦略」でも、持続可能な観光地域づくりに必要な財源確保に向けて、宿泊税等の導入の可否を含めた検討を行うこととしたところであり、今般、外部有識者による「観光振興財源検討会議」を設置することとしました。
この会議は、観光・財政・税政の分野で全国的に活躍されている大学教授のほか、県内経済団体、宿泊事業者の代表など10名で構成しており、第1回会議を来週28日(水)に開催予定です。
今後は、本会議での議論に加え、各地域の環境関係事業者の皆さんとの意見交換を通じて、様々なご意見を伺いながら、まずは導入の可否について、慎重に検討を進めていきたいと考えています。なお、会議は一部非公開としますが、会議終了後には担当部署から内容の発表を行う予定です。
配 布 資 料:大分県観光振興財源検討会議について [PDFファイル/212KB]
第165回九州地方知事会議・第47回九州地域戦略会議について
第165回九州地方知事会議および第47回九州地域戦略会議が、5月28日~29日にかけて福岡県で開催され、私も出席します。
今回の知事会議では、南海トラフ地震に備えた広域応援体制、また新生シリコンアイランド九州の実現に向けた基盤整備などについて、国に対する要望・提言として、13の特別決議を取りまとめる予定です。
また、戦略会議では、「九州創生アクションプラン」の第2期が昨年度で終了したことから、今後5年間を見据えた「第3期プラン」の審議を行います。
特に、大分県は「防災・減災対策高度化プロジェクト」のリーダーを務めており、AIやドローン等の先端技術を活用する優良事例の横展開など、官民連携でしっかり取り組んでいきます。
広域交通ネットワークの課題も非常に重要ですので、知事会での議論を経て、全国知事会に意見を上げていきたいと考えています。
配 布 資 料:第165回九州地方知事会議及び第47回九州地域戦略会議の開催について [PDFファイル/73KB]
記者質問
第1回大分県観光振興財源検討会議の開催について
(記者)
宿泊税の導入について、現時点で税額や確保額などのたたき台はあるか。
(佐藤知事)
現時点では予断を持たずに議論をしていこうというスタンスですので、額をいくらにするとか、総額でどれぐらいを目指すとか、そういったところまでは決めていません。その前段階として、観光振興の財源のあり方ということで、宿泊税も一つの選択肢として検討していこうということで進めているところです。
(記者)
別府市の阿部副市長が会議に入っているが、別府市ではすでに宿泊税の検討委員会が設けられているなかで、今回の県の会議での議論とどうリンクさせていくのか。
(佐藤知事)
別府市の長野市長ともお話をしており、これは全県的な課題なので、県としてもしっかり進めてもらいたい、とご意見をいただいています。その流れもあり、阿部副市長に県の検討会議の委員として入っていただき、連携を取りながら進めていこうとしています。
この会議の設置にあたっては、18市町村にご意見を伺いましたが、別府市だけで宿泊税を導入するよりも、導入するならもっと広い範囲の方がいいんじゃないかという意見が多くありました。必ずしも宿泊税を導入するべきという意見だけではありませんけれども、やるなら県全体で連携した体制の方が望ましいといった考えが多かったと認識しています。
そのため、別府市はもちろん、他の市町村とも意見交換を重ねながら、しっかり検討を進めていきたいと思っています。
(記者)
財源の確保策を講じる上で、どういったところに財源が必要だとお考えか。
(佐藤知事)
観光を推進するうえで、観光の魅力をPR・発信していくのは大変重要だと感じています。例えば、先日台湾を訪問した際にも、台湾の方々から、大分の温泉のことは知っているが、温泉以外に何があるんですか、と聞かれることが結構ありました。
私たちはいろんな発信をしているつもりですが、それでもまだまだ魅力が十分に伝わってない部分があるんだなと、改めて感じました。
そうした意味でも、広報・PRの強化だったり、観光の環境整備だったり、いろんな取組が必要ですし、それには財源があればあるほどできることも増えていきます。
宿泊税は、宿泊者にご負担をお願いすることになりますから、旅館やホテルの方々にとっては、宿泊者からいただく料金等が上がりますので、宿泊者の負担感を心配するという方もいらっしゃいますが、宿泊関係者からも導入を求める声も聞かれます。もっと観光政策を充実させて、魅力をどんどん発信していくことが大事という声は多いです。そういう観点からも、宿泊税のような新しい財源のあり方をしっかり検討していきたいと考えています。
(記者)
先ほど、温泉以外の知名度が低いという話がありましたが、それ以外に、交通網の不足など、観光に関する課題はどういったことがあると認識しているか。その点は、この会議でどう話し合いたいか。
(佐藤知事)
この会議は、宿泊税などの、財源の議論が主になります。
しかしながら、観光については、魅力の発信や、地域ごとの連携をどう図っていくか、というところも大きな課題になっていると思います。
例えば今年は、宇佐神宮が御鎮座1300年を迎えることから、秋には勅祭が行われますが、それまでの間に、将棋の名人戦が行われたり、様々な行事を行うこととしており、日本全体に大きな発信ができました。
名人戦の際には、永瀬九段は宇佐の安心院に泊まられて、すっぽん料理を食べたそうです。安心院にはすっぽんやワイナリーのほかにも、魅力のある食や宿泊施設があることから、温泉に加えての魅力として発信されました。
地域間の連携をどう作っていくかも、さらに取り組んでいく必要があると思っています。サンリオエンターテイメントさんは、ハーモニーランドのエンタメリゾート化を前から言われています。ハーモニーランドの周辺には、宇佐神宮、安心院、るるパーク(大分農業文化公園)があり、また湯布院もすぐ近くですし、別府ケーブルラクテンチや城島高原パークもあり、地獄めぐりもあります。こうした各所と連携しながら周遊観光してもらえるようなネットワークを作っていけるといいのではないかと思います。
その時に、どうしても車社会なので、車でしか行けないというのが1つ弱点となっております。
ですので、例えばハーモニーランドについては、8月から10月にかけて大分空港から杵築駅、そこからハーモニーランドまで行くバスを実証運行する予定です。そういう公共交通をどう整備するかも課題になってくると思っています。
(記者)
この委員の中に交通政策の教授がいます。全国的には交通税などの議論もあるが、観光に関連する交通の財源など、宿泊税以外の選択肢も含めて検討する予定か。
(佐藤知事)
今の段階では、交通税について検討する予定はないと認識しています。ただ、こういう検討会なので、議論の中でそういう話が出てくる可能性はあります。
また、先ほど財源の使途の話がありましたが、公共交通をもっと充実させるために使うべきだという意見や、観光の魅力発信の話なども出てくる可能性があります。
一方で、宿泊税は宿泊者に余分に負担してもらうことになるため、観光客の動向に悪影響が出ないか、隣県には宿泊税がなくて大分県にはあるとなると、敬遠されて他県を選ばれてしまうんじゃないか、という議論も当然あると思います。
ですから、広くメリット・デメリットを並べて、一つひとつ丁寧に検討していく必要があると思います。
(記者)
令和8年3月末までに、概ね3~5回の会議を開催し、宿泊税を導入するかしないかといった方向性をまとめる予定か。
(佐藤知事)
令和8年3月末までに、概ねの方向性を出していただく予定です。
この会議は検討会議ですから、それを受けて県庁内でも議論します。最終的に税をかける時には条例が必要になりますので、議会でもしっかり議論していただき決めていくことになります。
(記者)
観光振興財源は全県での導入を検討するという理解でよいか。 また、財源の使い道として、PRや自治体間の連携、交通関係などが挙がっていたが、それ以外に想定している使い道はあるか。
(佐藤知事)
県が導入する場合は、基本的に全県での導入になると思います。
使い道については、先ほど申し上げたような内容が中心になると思いますが、例えば宿泊税については目的税的な性格を持つと思いますので、委員の皆さんとそのあたりもよく議論していただいて、方向性についてご提言いただきたいと思っています。
婚活イベントについて
(記者)
ユニークな取組を続けており、知事ご自身にも思い入れがあるのかと思ったが、こうした様々なアプローチを継続していく意義は。
(佐藤知事)
アンケートによると、結婚を希望されている方は、男女ともに80%以上いらっしゃるのですが、出会いの場がないという理由で、なかなか良い機会に恵まれないという声が多いようです。そのため、そういった方々に対して出会いの場を提供することは大きな意義があると思っています。
OITAえんむす部 出会いサポートセンターでは、今までに235組の成婚実績があります。この出会いのサポートをさらに強化していけば、もっと多くの素敵な出会いが生まれるんじゃないかと思います。
こうした取組は、ただ出会いの場を提供するというだけではなくて、希望する方々がちゃんと結婚できる社会をつくっていく、子育て支援とか少子化対策の充実にもつながっていくと思います。
実際結婚された方は、こどもが2人くらいいることが多いようです。大分県の出生数は、一番多かったときは42,000人くらいでしたが、今は年間6,000人ちょっとで、7分の1くらいになってしまっています。
結婚する方の数も、年々減っており3,500件くらいになっています。婚姻数が大きく影響してくると思いますので、そういう意味でも、婚活イベントは少子化対策の一環としても非常に有効だと考えています。
(記者)
ホーバーを利用した婚活イベントでは、実際に動く中で行うのか、それとも乗るだけか。
(佐藤知事)
30分程度の周遊を予定しています。周遊したあとに、歓談の時間を設けたり、イベントに参加していただく、という流れになります。
令和6年度農林水産業への新規就業者・企業参入の状況について
(記者)
農業分野の企業参入の21社は、過去最多か。
(農林水産部審議監)
過去最高は平成22年でありまして、近年は20とか21件あたりで推移しています。
第165回九州地方知事会議・第47回九州地域戦略会議について
(記者)
南海トラフ地震が発生した際、大分県は佐賀県から支援を受けることになっていると思うが、九州地方知事会議の議題では、具体的にどんな内容が話し合われる予定か。
(佐藤知事)
南海トラフ地震が発生した時に、具体的にどのような支援を行っていくのか、また受援計画の確認をすることになります。各県でどんな取組をしているかについての情報交換もしながら、お互いに参考になることがないか、検討を進めていく予定です。
(記者)
例えば交通ルートや宿泊場所の確保といった点について、準備状況はどれくらい進んでいるのか。
(佐藤知事)
現時点では、個々の宿泊先などの具体的な検討まではまだ至っていないかと思いますが、もしよろしければ、防災局に別途取材していただければと思います。
南海トラフの新たな被害想定も出てきていますので、それを踏まえて詳細な計画に落とし込んでいく、という段階になります。
(記者)
先ほどのお話以外で、知事として今後議論していきたいテーマや、提案を考えていることはあるか。
(佐藤知事)
広域交通ネットワークは大事なテーマだと思っています。宮崎県の河野知事とも連携が進んできましたし、東九州新幹線では、福岡県・宮崎県・鹿児島県・北九州市と一緒に要望活動を行っています。
またもう一つ大事なのは、半導体関連と自動車産業です。米国の政策も含めて国際的な影響も出ていますし、自動車産業の話では、EV関連で日産の動きなどもありますが、中期的に見たら九州を支える重要な産業分野です。
そういった中で中九州横断道路の進捗状況など広域交通と絡む話もありますし、人材の確保も含めて、今後の議論の中でも非常に重要だと思っています。
令和6年度県外からの移住状況について
(記者)
大分県への移住者が1,746人と、毎年増加していることに関する受け止めは。また、四国の高知県や愛媛県では年間2,000人以上の移住者がいるとも聞くが、そうした県と比べた場合の認識はいかがか。
(佐藤知事)
移住者が毎年増えているのは、これまで積み重ねてきた努力の成果が出てきているためだと思います。ただ、もっと多くの移住者を受け入れている県もありますから、それらの取組を学びながら、さらに力を入れていきたいと思っています。
最近は、首都圏のように人口密度が高いところで生活・仕事をするよりも、地方に移住して生活するメリットが認識されるようになってきています。
また、子育て支援が充実している自治体もあります。あわせて実際に移住してきた方々からは「自然が豊か」「子育てしやすい」「農林水産業に触れやすい」「今までの経験が観光などで生かせる」など、いろいろなメリットを聞いていますので、そうした魅力をしっかり発信していきたいと思います。
最近では、2か所住まいや転職なき移住のような新しい居住スタイルも広がっています。例えば、東京や大阪の会社に勤めながら、普段は大分に住んでテレワークで仕事をして、月1回くらい出張するというスタイルです。大都会と田舎暮らし、平日と週末での2か所住まいなど、いろんな暮らし方・働き方が選べるようになってきていて、それによって生活の満足度も高まっていると感じます。
ですので、大分県としては移住の多様な形を提案していくことで、交流人口の拡大や地域コミュニティの活性化にもつなげていきたいと思っています。
(記者)
大分県の移住者増は、どういった施策によるものだとお考えか。
(佐藤知事)
スキルアップ移住の促進支援策も1つだと思います。加えて、例えば国の制度では、東京圏からの移住者にしか補助が出ないことが多いのですが、大分県では東京圏以外からの移住者にも支援を拡充しています。
他にも、例えば大分市では「同居・近居」世帯に対する住宅リフォーム支援、県北では住宅そのものを提供するような市町村もあります。こうした地域ごとの取り組みが、移住を促進する上で、非常に大きなプラスアルファになっていると考えています。
(記者)
福岡県からの移住者が全体の29.1%を占めており圧倒的に多いが、なぜ福岡県からの移住者が多いのか、県としての分析は。
(佐藤知事)
福岡県とは距離的に近いので、移住しやすいというのが一番の理由だと思います。
もともと行き来が多かったり親戚が大分にいたりという方もいますし、生活の移行がしやすいのだと思います。特に県北の方では自動車産業などが集積していて、福岡と大分を行き来しながら大分で働くことで、「ここに住むのもいいな」と思って移住を決めた、というケースもよく聞きます。
(記者)
移住者の市町村別データを見ると、日田市、由布市、大分市の順で多いようであるが、各市の特徴は。
(佐藤知事)
あくまで感想の範囲ですが、お答えします。
まず由布市については、温泉など観光資源のブランド力があり、実際に訪れてこんなところに住みたいと思って移住される方もいて、移住後にカフェを開いたり、自分のやりたいことを実現しているケースもあります。
また、大分市ではいろいろと制限がありますが、由布市内の挾間町などは建築規制が少なく、一戸建てが建てやすいといった事情もあると思います。
日田市については、おそらく福岡との距離の近さの影響が大きいと思います。文化的にも共通点が多く、馴染みやすいという点もあるかもしれません。
大分市については、コンパクトな都市機能が整っているのが魅力だと思います。
例えば、美術館やデパート、市の公共施設などが身近にそろっていて、利用しやすい。また、比較的ゆったりした暮らしができると感じる方も多いのではないかと思います。
さらに、東京や大阪ではなく、地方の中核都市で落ち着いて暮らしたいと考える場合、大分市のような都市は候補になりやすいと思います。医療機関も充実していて安心感がありますし、マンションの購入費も都市部に比べれば抑えられます。
また、大分市には企業の支店やコンビナートも多く、かつて転勤で住んだ経験があって、住みやすかったからと戻って来られる方も多いです。
これらは私の感想であり、分析ではありませんのでよろしくお願いします。
ホーバークラフトについて
(記者)
定期運航の目処が立っていない状況だが、万博も始まり空港利用者も増えるなかで、こうした状況を知事はどう受け止めているか。また、現時点で最新の見通しはあるか。
(佐藤知事)
前回の会見の時から状況は変わっていません。ただ、そんなに長引かないんじゃないかと期待しています。九州運輸局からいろいろ意見を聞きながら準備を進めているところです。
まだ具体的な目処は立っていませんが、県としては、大分の魅力を高めるためにホーバーは非常に大きな役割を果たすと思っています。万博で訪れるインバウンドのお客様にも利用していただければ、強いアピールになるはずです。
そのためにも、安全性をしっかり確保したうえで、一日も早く定期運航が開始されることを望んでいます。あわせて、婚活イベントでの活用など、「ホーバーに乗れる」という魅力も積極的に発信していきたいと考えています。
(記者)
例えば、夏休み前や万博期間中など、概ねの目安はあるか。
(佐藤知事)
最終的に九州運輸局の許可が出ないと就航できません。安全性が確認されない限り、運航できないというのは当然のことです。トイレ問題もその中に含まれていますが、30分程度以上の運航時間が見込まれる場合の運航の考え方など、整理すべき事項もあります。そういうことを踏まえると、まだはっきりした目安は申し上げにくいというのが現状です。
(記者)
トイレ問題については、まだ明確な結論が出ていないということか。
(佐藤知事)
最終的な決着がついたとは認識していません。
日産自動車の経営再建計画の影響について
(記者)
国内の工場閉鎖は関東方面の工場だとも言われおり、北九州の工場への影響があるかはまだ分からないが、大分県内にも日産関係の工場に部品を供給している企業がある。県内経済への影響や、今回の一連の動きについてどう見ているか。
(佐藤知事)
日産の経営再建がいよいよ動き出したということで、日本全体で心配されていると思います。特に追浜や平塚あたりは、大変ご心配されているんじゃないでしょうか。
大分県内には日産の工場はありませんが、福岡県には日産自動車九州株式会社と日産車体九州株式会社があります。この2社には、大分県の自動車関連企業会の活動に協力していただいています。
日産自動車九州では約4,500人、日産車体九州では約1,100人が働いています。今のところ、この2つの工場名は報道等で挙がっていませんが、今後どのような影響が出るかは分かりませんので、引き続き動向を注視していきたいと思います。
以前、ダイハツの工場が停止した際に、相談業務などいろいろな対応を行ってきました。今回も必要に応じて、しっかり対応できるよう備えていきます。
特に、経営再建計画の中にある部品の種類や数量の削減などが進んでいくと、日産の工場だけでなく、そこに部品を供給している関連企業にも影響がでる可能性があります。
自動車関連企業会と連携しながら、情報収集と影響把握をしっかり行っていきたいと思っています。
第83期名人戦七番勝負 第4局宇佐神宮対局について
(記者)
2年連続で名人戦が県内で開催されたことについて、率直な感想は。
(知事)
まず2年連続県内で開催されたことは本当にありがたく、嬉しいことだと思っています。全国的にも注目されますし、去年は別府、今年は宇佐と、特に宇佐神宮の御鎮座1300年をしっかり発信できたのではないかと思います。また、勝負飯などを通じて、大分の味の魅力も広く知っていただけたと思います。
私も前夜祭に出席しましたが、藤井名人や永瀬九段は、本当は対局のことでもう頭がいっぱいだったはずなんですが、それでもファンの皆さんの前に立って、トークを披露したり、宇佐神宮を訪問したりと、そうした姿を見ると、本当にプロとして立派だなと感じました。将棋の振興やファンを大切にしてくださっていて、若いお二人ですけど本当に素晴らしいと思いました。
勝負ではギリギリの精神状態だと思います。対局が終わると、かなりの疲労があるはずですけど、永瀬九段は安心院ですっぽん料理を食べますと仰ってましたので、それは精力がつきますよと言ったら、にこっと笑っておられました。
宇佐を楽しんでもらいながら、全力を出し切っていただけたとすれば、とても嬉しいです。こうした名人戦のような大会で多くの方に来ていただけるのは、本当にありがたいことだと思っています。
今後もそうした皆さんが、大分に来てくださる機会が増えるとよいと思っています。
(記者)
現在、大分出身のプロ棋士はいないようだが、名人戦のような大会は、地域経済の活性化にもつながると思う。今後もこのような対局の誘致を進めていくお考えはあるか。
(佐藤知事)
もちろんその思いはありますが、今回の名人戦は県が誘致したわけではなく、宇佐神宮御鎮座1300年の記念事業として、地元の商工会議所が中心となって事務局を担い、特に青年部の若い方々がアイデアを出し、招致に向けて尽力されたと伺っています。
昨年の別府市での開催も、別府市制100周年を記念した取組の一環で、別府市が誘致したものです。
県としては、こうした多様な主体がそれぞれ努力して、著名人を招くことは本当に素晴らしいことですし、地域の魅力発信や活性化にもつながると考えています。
農林水産大臣の発言について
(記者)
先日、農林水産大臣(※5/20時点)が佐賀市でのお米に関する発言が物議を醸しています。知事として率直にどう感じたか。
(佐藤知事)
今は流通も含めていろんな課題が出てきている時期ですので、やはり発言には注意を払っていただくのがよいのではないかと思います。
(記者)
率直に、どう感じたか。
(佐藤知事)
いや、本当に買ったことないのかと思いました。
正確にどう発言されたのかはわからないので、総理から注意を受けたということをニュースで見た程度です。
米の価格がなかなか下がらない問題は、流通の在り方なども含めて大きな課題だと思っていますし、そういう背景がある中での発言ですので、やっぱり注意が必要かなと感じています。あくまで報道を見た範囲での感想です。
大阪・関西万博について
(記者)
来週から万博会場で再生可能エネルギーをテーマにした県のブース出展があると思うが、大分の魅力をどのように発信したいか、また誘客への期待は。
(佐藤知事)
大分は地熱発電が日本一ですし、太陽光など自然エネルギーの活用も盛んです。例えば温泉熱を使ったバナナ栽培や、地熱を活用したパプリカの生産など、農業にも活用されています。
また、森林県でもありますので、森林を生かしたJ-クレジットの創出などの取組も進めています。地球環境の観点から、そういった点をしっかりとアピールしていきたいと思っています。
(記者)
大分の魅力を世界に発信するチャンスだと思いますが、その点はいかがか。
(佐藤知事)
大分といえば温泉と言われますが、地熱も含めてどのように活用されているのか、地域の魅力の一つとして、再生可能エネルギーについても発信していきたいと思います。
(記者)
万博関連では、すでにサンリオとの連携や、宇佐神宮御鎮座1300年などと絡めたイベントが行われているが、ここまでの万博効果について、何か反響が届いていれば。
(佐藤知事)
万博が始まる前までは、県内でもあまり盛り上がっているようには感じなかったのですが、実際に始まってからは盛り上がりもあり、会場で大分の魅力発信をさせてもらったりしています。
また、万博が開催されることもあって、大分ハローキティ空港の取組が実現したところもあります。万博に来るインバウンドのお客さんを呼び込むには、世界的に人気のあるキャラクターであるハローキティの名前を使用するのが効果的ということもあって、多くの方に賛同とサポートをいただいて実現したところです。
また、地域の特産品や地域資源を磨き上げて素材集にして発信したり、県内でミニ万博のような、おおいた地域博覧会を、秋に開催する準備も進めています。
世界に本県の魅力を発信するというのは限界がありますが、万博で日本に来ている方をターゲットに発信ということは効率もいいと思います。そういう意味では、もうすでに一定の効果が現れてきているのではないかと考えています。
(記者)
もうすでに効果を実感されているということか。
(佐藤知事)
万博の開催がなかったら、大分ハローキティ空港にもならなかったかもしれませんし、それが日本でもメディアの皆さんに取り上げてもらったり、台湾ではSNSなどでも紹介されています。
そういう意味で、すでにいろいろな効果が現れてきていますし、今後もさらにいろんな取り組みができると思っています。




