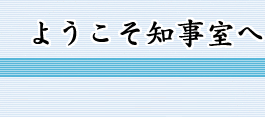
令和7年6月3日知事定例会見
動画はYouTube「おんせん県おおいた公式」へ
日時:令和7年6月3日(火曜日)13時30分~
場所:第一応接室
記者会見時に配布した資料を掲載します。

第165回九州地方知事会議及び第47回九州地域戦略会議の結果について
冒頭に、先週参加した九州地方知事会議についてお話しします。
九州の各県知事や、経済界の皆さんが集まる九州地域戦略会議でも、活発な議論が出て、大変有意義な意見交換ができました。
九州地方知事会議では、まず南海トラフ地震に備えた広域応援体制について話し合いました。南海トラフ地震が起きた場合、佐賀県が大分県を応援することになっています。具体的には、今年の4月からそれぞれの担当課に職員を派遣しており、発災時にはしっかりとした対応ができるよう引き続き連携強化を図っていくことを話し合いました。
国への要望である特別決議については、「新生シリコンアイランド九州の実現に向けた基盤整備」や「ツール・ド・九州の更なる充実に向けた支援」という13の提言がとりまとめられました。
その中で、私からは、広域交通ネットワークの構築、特に東九州新幹線などの整備に向けた財源確保について説明しました。
現在、国の新幹線整備にかかる当初予算が800億円ほどしかなく、今の整備新幹線が終わってからでないと、基本路線に格上げされない状況です。そこで、具体的に貸付料の算定の適正化、国際観光旅客税、いわゆる出国税の活用などを提案し、決議文に盛り込まれ、今後、全国知事会でも議論される予定です。また、九州地方知事会の決議項目については、関係省庁にも提言を行う予定としています。
九州地域戦略会議では、「第3期九州創生アクションプラン」の7つのプロジェクトについて議論しました。大分県は「防災・減災対策高度化プロジェクト」のリーダーとして、私から災害対応にAIやドローンなどの先端技術を活用する事例の横展開、それから初動対応時の情報共有を円滑に行うためのガイドラインを策定していくことなどを申し上げました。
また、大規模災害の備えとして、電力の安定供給が重要であるということで、配布しているリーフレットの中の一番右のページに載っていますが、九州電力と四国電力の間の電力融通についても議論しました。これは、災害時だけでなく、産業発展のためにも非常に重要です。国の政策の項目にも入っていますし、九州電力も戦略会議のメンバーに入っています。
九経連の次期会長は九州電力の池辺会長が就任する予定ですが、この地域間の電力融通の整備には、およそ4,800億円から5,400億円かかる見込みです。これは、豊予海峡に豊後伊予連絡道路を建設するのにかかる費用とほぼ同じくらいです。両者を一体的に進めれば、国民負担も軽減できるため、プロジェクトがより進めやすくなるのではないか、という話もしました。
このように、特に大規模災害が起きて電力が全て停止してしまうような事態への備え、そして産業面でもこれから新生シリコンアイランドを推進していく上で高まる電力ニーズに対応するためにも、さまざまな取組をやっていこうと率直な意見交換ができました。
今後もこうした場を活用しながら、そして全国知事会の場も活用しながら、意見交換を進めていきたいです。
もう一つ、事前の事務方の調整の中で提案の項目からは外れていましたが、新幹線の料金に上乗せして、それを財源にしたらどうかということについても、私から議論すべきではないか、と説明しました。
これは東海道新幹線や山陽新幹線がつくられた際、大分県民も負担して出来上がってきたわけです。しかし、すでに新幹線が整備されている地域の皆さんは、今、新幹線がない地域に新幹線をつくるのは贅沢ではないか、人口が減る時につくるべきではない、という議論が出ることがあります。しかし、国の計画があり、最初につくられた地域については大分県民も負担してきたという経緯を考えると、逆に、新幹線がまだない地域の整備も、国を挙げて、それぞれ分担しながら取り組むべきではないかということを申し上げております。
あわせて、自然エネルギーの供給能力を向上させるために電力料金に上乗せして、太陽光発電や風力発電の普及を図ってきていますが、同じような考え方で新幹線の整備に取り組むことも重要ではないかということと、新幹線のネットワークが繋がることが、利用者の利便性のさらなる向上やJR各社の収益の向上にも繋がるという視点もあるのではないかということを申し上げました。
全国知事会への提案としては、九州知事会からは貸付料算定の適正化と出国税の活用の2つの項目になります。
出国税はご存知の方も多いと思いますが、日本人も外国人も日本を出国する際に1,000円が課税されます。これはインバウンド等が快適に旅行できる環境の整備に使うことになっていますので、新幹線が整備されることで旅行者がより便利に日本各地に行けるようになることから、目的に沿うのではないかという議論をしています。
新幹線の費用負担については、国の方で議論してもらわないといけない話ですが、新幹線の整備の議論が進むような問題提起はできたのではないかと思います。今後もこのような議論をさらに深めていきたいです。
配 布 資 料:なし
令和8年度政府予算等に関する要望・提言活動について
6月4日、5日の2日間、令和8年度政府予算等に関する要望・提言活動に行ってきます。
今回は「安心」「元気」「未来創造」の大分県づくりとして、関係省庁に16項目を要望してきます。
近年、激甚化する災害に対応するための県土強靭化に必要な予算の確保や大分県版カーボンニュートラルに向けた財政支援の拡充、大分県が先駆的に取り組んでいる里親制度の国全体での創設などを新たに盛り込みました。
また、広域交通ネットワークの充実や東九州新幹線等の整備、今回は「等」と書いていますが、四国新幹線、大阪から四国を通って大分まで到達する路線の整備も含め、話をしてきます。
さらに、中九州横断道路などの高規格道路の早期完成、物価高騰で厳しい状況にある県内中小亊業者への支援、観光振興や農業農村の整備に必要な予算措置、遠隔教育の推進なども要望します。
遠隔教育は4月からスタートしていますが、遠隔教育に携わる教員の予算が、文部科学省が定める予算の枠外になっているため、定数外となっています。文科省が遠隔教育やDX化を推進する政策を掲げているのであれば、ぜひ枠内にして、国の予算措置も講じてほしいという要望をしていきたいと思います。
このように、国にしっかりと働きかけ、国と連携することが重要です。先ほどの広域交通ネットワークも、国の施策として、日本全体をどう効率よく、強く、そして災害に強い国づくりをしていくかという視点で見てもらう必要があります。
ルートの話もよく出ますが、やはり九州全体、また日本全体の高速鉄道網の整備を国全体としてどう進めるかという視点が重要です。
特に、リニア新幹線で東京と大阪が1時間で結ばれますので、そことどう繋いでいくかという議論が必要です。これは昔の日本列島改造論とは異なるテーマです。
大分から四国を通って大阪に新幹線で行くと2時間で行けます。九州知事会のあと博多から大阪まで新幹線で移動しましたが、2時間半かかりました。したがって、大分から四国を通って大阪に新幹線が通ると、30分早くなるわけです。そうした意味で関西と関東が一体になるので、大分が九州の一番東側にあるというアドバンテージを非常に生かせる取組の一つになります。新幹線が通れば、四国を通って大阪まで来られるようになるわけですね。
そういったことについても、これからも進めていきたいと考えており、今回の要望活動で伝えていきます。
配 布 資 料:政府予算等に関する要望・提言活動について [PDFファイル/643KB]
県立夜間中学の入学生募集開始について
県では、さまざまな事情で教育の機会がなかった方々に学びの機会を作るため、県立夜間中学の令和8年4月の開校に向けて、準備を進めています。
先月、大分県立夜間中学校支援委員会が開かれ、基本構想や生徒募集などについて議論が行われました。
本日は、機運を盛り上げようと、ホルトホール大分にて夜間中学に関するシンポジウムが開催されています。熊本県立夜間中学である「ゆうあい中学校」から校長先生と生徒3名が参加し、夜間中学における学びなどについてパネルディスカッションが行われています。
そして、明日6月4日から、入学生の募集を開始します。チラシに相談窓口の電話番号やメールアドレスを記載していますので、そちらをご覧いただき、ご相談ください。
チラシの裏面に記載していますが、7月から8月にかけて、県内6会場で入学相談会を実施します。夜間中学への入学を考えている方や興味のある方、関係者などもぜひ参加してください。
令和8年4月の開校に向けて、教育委員会と協力してしっかり準備を進めていきます。
配 布 資 料:大分県立夜間中学生徒募集 チラシ [PDFファイル/229KB]
大分県立夜間中学入学相談会 チラシ [PDFファイル/297KB]
大分県総合防災訓練の実施について
今週6日金曜日に大分県総合防災訓練を実施します。
昨年度は11月に開催しましたが、今年は出水期前に前倒しして実施することにしました。これは、洪水などが心配される出水期に向けて、関係機関との連携を確認するためです。
今回の訓練は、南海トラフ地震が発生したという想定で行われ、県と市町村、自衛隊などの関係機関が参加し、討議型で連携を確認します。また、16時からは各部局長による災害対策本部会議の運営訓練を行います。
今回の訓練テーマは、能登半島地震を踏まえた防災対策の強化の3つの柱である、孤立集落対策の強化、被災者支援の強化、応援・受援体制の強化とし、関連したシチュエーションで対応手順と連携の確認を行います。
間もなく出水期を迎えるにあたり、事前点検なども行っていますが、合わせて、県庁内や関係機関との訓練を通じて、防災体制の強化に取り組んでいきたいと考えています。
配 布 資 料:令和7年度 大分県総合防災訓練(図上)の概要 [PDFファイル/206KB]
台湾での教育旅行相談会及び旅行社向け観光商談会について
4月2日にタイガーエア台湾の台北-大分線が就航し、搭乗率は好調に推移しています。
これを機に、台湾からの観光客をさらに呼び込むため、6月に台湾で、教育旅行相談会と県単独の観光商談会の2つを行います。
まず、教育旅行相談会は、日本政府観光局(JNTO)が主催するもので、台湾の教育関係者と個別に相談を行うものです。大分県の参加は8回目となり、6月10日が台北、11日が高雄で開催されます。台湾各地から小中高の学校関係者や旅行会社など、合わせて100名が参加する予定です。
昨年は台北で20校、高雄で10校と面談し、県内の小中高校の状況に加えて、学校交流や農学体験などの魅力をPRしました。その結果、昨年を4団体上回る14団体と交流できました。
これは、台湾の小中学校などから、大人数ではありませんが大分に来てくれたということです。教育旅行の誘致は、その後、今度は家族で行こうといったリピーターにも繋がるので、一つでも多く誘致を実現できるよう努めていきます。
もう一つは、県単独での台湾旅行会社との観光商談会です。こちらは6月12日が台北、13日が高雄で、教育旅行相談会と同様に8回目の開催となります。本県からは宿泊観光施設など28団体が参加します。台湾側も旅行会社など約100社が参加する予定です。
去年の秋には私も参加しましたが、台湾の旅行会社の方々は非常に熱心で、多くの質問をいただきました。温泉以外の魅力は何かといった質問もたくさんあり、活発な意見交換ができました。今年も100社が参加し、この商談会をきっかけに、新たな取引が始まったり、団体が増えたりすることも多いので、取引の拡大と連携の強化を図っていきます。
今年度は、このほかにも教育関係者を大分に招待するツアーの実施や、台湾での旅行博への出展、観光プロモーションなどを行います。現在TSMCとの関係で台湾との往来が非常に増えているので、それにふさわしい取組を進めていきたいと考えています。
配 布 資 料:台湾での教育旅行相談会及び旅行社向け観光商談会について [PDFファイル/349KB]
記者質問
令和8年度政府予算等要望について
(記者)
項目一覧で16項目挙げられているが、特に知事として力を入れているものはあるか。
(佐藤知事)
これは、それぞれ担当部長と一緒に行き、各省庁に要望します。ですから、優先順位はなく、全て重要です。
県の行政は幅広く行っていますが、教育の振興も大事ですし、広域交通ネットワークの充実も大事です。また、例えばこどもの安全対策やこども子育て支援も大事です。
全て同じように、しっかりと要望していきます。要望先では、大臣などもご自身の所掌のところを熱心に聞いてくださいます。全てが最も大事だというつもりで要請してきます。
(記者)
各部で省庁に行くと思うが、大臣との面会が行われるものはあるか。
(佐藤知事)
実際に面会が決まっているところは、いくつかあります。
(総務部長)
予定ですが、国土交通大臣、そして特命担当大臣など、複数のアポイントが取れています。あくまで予定ですので、現地でまた詳しく説明したいと思います。
(記者)
新規項目の里親制度について、大分県は先進的というお話でしたが、国に対する要望点は。
(佐藤知事)
これはですね、大分県が他県に先駆けて、特に日本財団などの支援も受けながら取り組んでいることで、主に2つあります。
1つ目は、乳幼児の短期緊急里親制度の創設です。児童相談所に保護されたこどもたちには、やはり家庭的な環境で過ごしてもらいたいと考えています。その際に、里親の方がすぐに受け入れられれば良いのですが、すぐに受け入れが難しいなど、緊急時のために待機してもらっている里親がいらっしゃいます。そういった方々にお願いする制度を、「短期緊急里親制度」と呼んでいます。1か月程度までの短期間、こどもを預かってもらう制度です。例えば、令和6年度では、短期の里親としてこどもを預かってくださった方が6組くらいいて、延べ523日くらい保護していただいています。この制度を県単位ではなく、国として全国ベースでぜひやってほしいというのが1つ目です。
2つ目は、里親レスパイト専任職員配置の制度化です。里親になっていただくと、こどもを預かることになりますから、大変なこともあります。里親さんが少し休める制度「里親レスパイト」に対応するための職員を、大分県独自の取組として、別府と中津の児童家庭支援センターに配置しています。
こうした職員の配置を国として制度化してもらい、県単位でやるのではなく、国全体でこの取組を進めてほしいというのが2つ目です。
本当に数%の割合ですが、児童相談所に保護されるようなこどもたちがいるわけですが、そうしたときに、全国でしっかりと制度化して対応できるようにすべきと思います。
これら2点が新しい要望です。
(記者)
遠隔教育配信センター自体は、どの地域でも質の高い教育を受けられるようにと設置されたと思うが、先週、教育委員会の通学区域制度検証委員会が、通学区域については、現在の全県1区制度をベースに改革を考えていくべきだと答申した。まず、この答申についての知事の受け止めと、その中で遠隔教育事業をどのように位置づけるか。
(佐藤知事)
基本的に全県1区をベースとするというのは、今後教育庁が答申を受け、さらに内部で議論を進めていくことになりますが、答申の中にはさまざまな制度の、例えば最初から第二希望も書けるようにするなど、色々な提言がされていると思います。答申自体は非常に意味のある提案をいただきましたので、これから、さまざまな場で議論がありますから、それを踏まえて進めていくことになると思います。
そして、この遠隔教育は、全県1区制度とは別の議論ではあります。しかし、遠隔教育によって、これまで特定の学校に行かないと受けられなかったような授業が、自分が卒業した中学校の近くの高校で、遠隔教育を使って受けられるようになります。
先日、教育センターで「グローバルリーダー育成塾」があり、私も参加しましたが、約800人の高校生が集まりました。スタンフォード大学やAPU(立命館アジア太平洋大学)と連携したオンラインによる講座を開講しており、その閉講式も行われました。広い意味での遠隔教育ですが、大分県が独自に先進的に取り組んでいるものです。
このような遠隔教育は、実際に授業を受けているのと同じか、それ以上の質が得られます。これはこれで進めていきます。
通学に長い時間を使ったり、下宿したりしなくても、自分の卒業した中学校の近くの高校で学習できるようになるというのは、全県1区の議論においても、検討すべき材料の一つになるのではないかと考えています。
県立夜間中学の入学生募集について
(記者)
どのような方に来てもらいたいか。県民の方に入学募集にあたって、どう呼びかけたいか。
(佐藤知事)
やはり様々な事情があって中学校に通えず、中学校卒業となった方に参加いただきたいと考えています。中学校を卒業したけれど、もう一度学び直したい、十分にその時の学びができなかったという思いがあって、もう一度勉強し直したいという方は、ぜひ入学をご検討いただきたいです。中学校での学びをもう一度やりたい方には、広くご参加いただきたいと考えています。
大分市の入札妨害について
(記者)
大分市の除草業務委託をめぐる入札妨害事件について、市長経験者である知事の受け止めは。
(佐藤知事)
法令遵守は非常に重要なことですので、それに沿って業務を行うことは大事なことですけども、市の職員の関与自体もまだ明らかになっていません。私が市長を退任してから1年2か月以上経って発生した事件でもありますので、これ以上のコメントは差し控えたいと思います。
ただ、所感を述べよと言われれば、一般論になりますが、県庁の職員は当然ですけど、大分市の職員も、大部分の職員は矜持と使命感を持って仕事をしていると私は思います。おそらく99.99%くらいはそうだと思います。私も市の職員と一緒に仕事をしていましたから、そう感じています。
これを100%にするべく、例えば目配りをしたり、励ましたりしながら、務めていくのが、リーダーである首長の役目ではないかなと、おそらく民間企業の社長も同じだと思いますし、あらゆる組織でも、そうあるべきだと思います。知事としての最も重要な役割だと感じています。
私自身、今もそうですが、入庁式の訓示では必ず法令遵守、コンプライアンスが何よりも重要だと伝えています。法令を遵守して仕事をするのは絶対に必要なことなので、これから仕事をする上で絶対に忘れないでくださいと話しています。
また、係長級研修や課長級研修の際にも、法令遵守をしっかりしてくださいと繰り返し話しています。部長会議などでも話していますが、そういうことであります。
大分市で8年間市長を務めましたが、その間も同様にしていました。
今後、事件の話がどうなるか分かりませんけども、私は市長職を離れてはいますが、もし本当に起こっていたんだとすれば、大変遺憾であり、残念な気持ちです。しかし、まだ捜査中ですので、色々と話しましたが、コメントは差し控えさせていただきます。
(記者)
今回逮捕された造園業者の取締役3名から、令和5年度に知事後援会に寄附がなされているようだが、市長時代からそのような寄附があったのか、知事になってからなのか、どのような繋がりなのか。
(佐藤知事)
稙田の方なので、支援者として後援会に寄附をいただいていると認識しています。ただ、適正に処理されていますので、それと今回の事件とは無関係だと認識しています。
(記者)
取締役の方から、社長が30~40年前から市議を通じて入札予定価格を聞いていたという供述が出ているようだが、知事が市長時代にそのような話を聞いたりしたことはあるか。
(佐藤知事)
ありません。そして、市議の倉掛議員も、自分の周りでも聞いたことがないとおっしゃっていました。これについては今捜査中ですから、事実は徐々に明らかになるかもしれませんが、私が市長時代も、知事になってからも、そのような違法なことをしているという話は聞いたことがありません。
(記者)
大分市の足立市長が先週の会見で、かなり以前から、職員から議員への情報漏洩があったのではないかと思うという発言があったが、その発言に対する知事の受け止めは。
(佐藤知事)
先ほど、もしかしたら質問がないかもしれないと思って少し話したことが、ある意味でコメントになります。
県職員は当然ですが、市の職員も大部分の職員は矜持と使命感を持って仕事をしていると思っています。何パーセントかは分かりませんが、99.9%の職員はそういう職員ですから、残りの職員を100%にするような取組が、首長には求められるのではないかなと思います。
あと具体的に、例えば議員さんが何か働きかけをしてきた時には、具体的にこうしてください、ということが県の内規の中にもしっかりあります。一方で、おそらく議会もそういうことをしないように、という取り決めをしていると聞いていますので、お互いにそういうことについては、絶対にやってはいけないという形で、もう体制的にもできているのが実態だと思います。
実際に何があったかについては、先ほども言ったとおり、捜査中なので、結果を見てみないと分かりません。私が市長を離れてからではありますが、元市長として、引き続き注視していきたいと思います。
やはり事実関係が何より大事だと思います。
市の職員自身がどう関与しているかも分かりませんから、そういうところも含めて、県警本部長には、今回の件も30年40年という話も報じられているので、しっかり捜査してくださいと要請しています。
(記者)
大部分の職員は矜持と使命感を持ってやっているとのことだが、足立市長が、昔からそういう情報漏洩などあったのではないか、と発言されていることに対して、知事のお考えは。
(佐藤知事)
それは捜査を見ないと分かりません。ただ、あったとすれば、やはり目配りが足りなかったという反省すべき点はあるかもしれませんし、もう一つは、コンプライアンスについては先ほども言ったとおり、繰り返し働きかけ、呼びかけ、励ましをしてきましたが、本当にあったとすれば、大変遺憾であり残念だという思いもあります。
ただ、そこはこれからの捜査を見てみないと、予断を持って判断し、発言するのは差し控えます。
(記者)
実際あったかなかったかは、今後の捜査の展開を見てからでないと分からないということだが、少なくとも、知事の市長時代に、そうした報告や相談はなかったと理解してよいか。
(佐藤知事)
申し訳ありませんが、相談や報告があったら、すぐに「やめろ」と必ず言うわけです。皆さんも考えていただければ分かると思いますが、そういうものがあって見逃したり、容認したりしていたら、本当に辞職しなければならないような事案です。
したがって、繰り返しになりますが、そのようなことについては聞いたこともありませんし、倉掛議員も自分の周りで聞いたことがないと言っていました。もし私がそれについて何か知っていたり、認識したり確知していたら、その段階で直ちに止めさせて是正に取り組んでいたはずです。8年間市長を務めましたが、そのようなことについては全く聞いたこともありません。それが事実です。
大分市官製談合事件について
(記者)
先日、官製談合事件で元環境部長(池永氏)の初公判が開かれたが、改めて知事ご自身が傍聴に足を運ばれた理由と、傍聴された上での感想は。
(佐藤知事)
まず、池永氏と最後に会ったのは、おそらく昨年の夏頃で、鶴崎公民館の落成式か夏祭りの時でしたが、当時は非常に元気でした。しかし、先日の公判で横顔しか見えませんでしたが、非常にやつれていて、体重も相当落ちたんじゃないかなという印象を受けました。非常にやつれていたなというのが1点です。
それからもう一つは、この会見の時にもお話ししましたが、事実関係が分からないので、それが捜査の過程において明らかになると思いますと、それを注視したいと思いますと言ってきました。
池永氏について言うと、公判を聞く限りにおいては、決裁権者ではあったけれども、どちらかというと巻き込まれたような印象でした。早川氏が、その前の公判の時に、池永氏をどう思いますかと裁判官に聞かれて、なんて答えたかご存じですか。早川氏は大変気の毒に思いますと答えているんですよね。どうもやはり、早川氏は池永氏とは、おそらく1回か2回、多くて3回ぐらいしか会ったことがないと言っていたようです。そういう中で、もう一度池永氏の公判がありますので、それを見てみないとわかりませんが、こうした状況を踏まえて、裁判官が刑罰を科すに値するような非難可能性があるのかどうかについての判断をどうするのか、注視していきたいと思っています。
防災庁の誘致について
(記者)
昨日、熊本県が政府要望に合わせて防災庁の誘致を表明したが、大分県の防災庁誘致に関する考え方は。
(佐藤知事)
大分県は防災庁の誘致について議論していません。災害時にしっかり連携できて対応できれば良いので、防災庁誘致に関してはそもそも庁内で議論していません。
(記者)
九州だと佐賀県と熊本県が誘致を表明しているが、関西広域連合は関西に必要だという広域的な意見もある。大分県知事として、九州に必要かというようなスタンスはあるか。
(佐藤知事)
九州の中で必要かという議論も、実は九州知事会などではしていないので、考え方はまとまっていません。私個人の意見を問われれば、全国どこで災害が起こるか分かりません。大分だと南海トラフ地震などが関係しますが、全国で災害が起こった時に、最も効率的に災害対応ができるような場所に防災庁があれば良いと考えています。ただ、やはり総理に近いところの方が良いのではないかという気もしなくはありません。これはあくまで個人的な意見です。
「通いの場」参加率日本一について
(記者)
「通いの場」の参加率が11年連続で日本一になった結果の受け止めは。
(佐藤知事)
「通いの場」は、大分県と市町村が一生懸命努力して、公民館などさまざまな場所に集まる場を作り、そこに高齢者の方々が多く来てくれています。これは、一時期ですが、健康寿命が男性1位、女性4位という全国トップクラスの結果にも表れていたと思います。
コロナ禍で「通いの場」が一時的に開けなくなり、男性の健康寿命は20位台に下がってしまいましたが、また「通いの場」が日本一になったということは、やはり高齢者の方々が外出する場所があり、意見交換ができたり、一緒に体操ができたり、あるいはこどもたちと触れ合ったりする場があるのは、元気で健康に長寿を全うするには非常に大事なことだと思います。したがって、「通いの場」が日本一になったことは非常に素晴らしいことであり、それがまた、男女ともに健康寿命日本一に繋がってくることを大いに期待しています。
(記者)
参加率は14%ということで、数字だけ見るとまだまだ広がる余地もあると思われるが、今後の周知啓発についてのお考えは。
(佐藤知事)
これは、さらに呼びかけをしていくことです。また、このような場でお話しするのも情報発信にもなると思います。それぞれの公民館など、さまざまな場で呼びかけていきます。
皆さんもご存知かと思いますが、参加者は圧倒的に女性が多いんですよね。男性が少ないんです。それでも男性が日本一だったのは不思議ですが、男性の方々も女性に負けず、そのような様々な場に来て、健康体操や教室などに参加いただけるように、さらに発信をしていきます。これも市町村とも連携しながらやっていきたいと思います。
備蓄米の流通と価格について
(記者)
農林水産省が随意契約を行った備蓄米が全国各地のスーパーに入ってきており、ネットでも売切れの声もある。価格が下がっている一方で、県内の農家や農協の方からは、価格下落を心配する声も上がっている。今回の備蓄米の随意契約と価格下落についての知事の考えは。また、農家の方のことも踏まえて、適正な価格はどのくらいだとお考えか。
(佐藤知事)
価格は非常に難しい問題ですので、やはりマーケットで決めていきましょうということで、標準米や銘柄米は4,000円以上になっていました。一方で、少し古くなったお米が、価格を下げようということで提供されはじめましたが、県内では6月1日時点では20箇所のスーパーの店頭に並んでいませんでした。しかし、「今後販売予定」や「6月初旬から随時販売します」「6月9日以降に販売します」といった張り紙があったり、2,000円や2,200円弱くらいで販売しますといった前触れがあるところはいくつか出てきています。まもなく販売が始まるのではないかと思います。
消費者の立場からすると安い方が良いのですが、同時に、やはり銘柄米を選びたい人が選べ、安ければ良いから手に入れたいという方は手に入れられる、というように選択肢が広がる形になるのが良いのではないかなと感じています。
今回、本当に米が足りないのではないかという議論もあれば、どこかに滞留しているのではないかという議論もあります。農政の総点検をして、その流通を適正にすることによって、その分の値段が下がっていくということもあるでしょうし、ずっと続けてきた減反政策を少し変えていかないといけないこともあるかもしれません。これは食料安全保障の問題です。広く議論をして、どこかに滞留していたり、投機的に買い占めしている人がいることでうまく流通していないのであれば、そこは是正していってもらわないといけませんし、その点検も合わせて必要ではないでしょうか。
いくらが良いかというのはなかなか難しいです。
(記者)
県内農家からは、不安の声が知事のもとに届いているか。
(佐藤知事)
私のところまで直接ありませんが、もしかしたら農林水産部には色々な意見が来ているかもしれません。今まではどちらかというと、「なつほのか」のような高温に強い品種を普及させないと米がたくさん採れないとか、気候の変化への対応を一生懸命やってきて、あとはブランド化していこうと取り組んできたわけです。
ところがやはり、農政の根幹の部分で議論が出ているので、やはりそれは注視して、それに対応した取組をどうしていくかというのは、確かにおっしゃるとおり、生産者の皆さんや、重要な役割を担っているJAの方々からも意見を聞きながら、取り組んでいかなければならないと思います。
(記者)
価格が下落したことにより、農家に対して所得補償をする検討が閣僚会議でなされているが、県の方でそういった補償を考える可能性はあるか。
(佐藤知事)
これは全国的な農業政策の中で議論すべきことなので、個別にそれぞれの県や市町村がやるような話ではないのではないかと私は思います。そこも含めて、これから様々な議論が出るのかもしれません。
長嶋茂雄読売巨人軍終身名誉監督の訃報について
(記者)
本日、長嶋茂雄さんがお亡くなりになられたが、知事の思い出や所感は。
(佐藤知事)
長嶋茂雄さんは、王貞治さんと並んで、私たちがこどもの頃のスター中のスターでした。こどもの頃の遊びといえばやはり野球であり、竹バットを振って野球をすることが多かったです。そして大分でも、ナイター中継はほとんど巨人戦でした。そういうことで、王さんと長嶋さんはやはりスター中のスターでしたね。
野球界の発展に大変貢献し、ご尽力いただいた方が逝去されたということで、長嶋さんとの直接の接点はありませんでしたが、長嶋さんは、私たちからすると、一番憧れるスポーツ選手でしたので、心から敬意を表し、ご冥福をお祈りしたいと思います。
(記者)
長嶋さんの現役時代のプレーや試合で何か印象に残っていることはあるか。
(佐藤知事)
一番印象に残るのは、野生の勘とでも言うのでしょうか、ボールが飛んできた時のグラブさばきの感性ですね。また、プレーで醸し出すスター性が、他の選手にはないくらい際立っていました。そのスター性が、いつもそのプレーを見る人を楽しませる、そういう天性のものがあった方ではないかと思います。特定のどの試合というわけではありませんが、いつもそう思いながら見ていました。まさに不動の3塁手でしたね。




