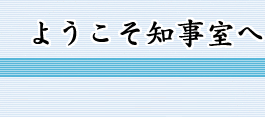
令和7年9月2日知事定例会見
動画はYouTube「おんせん県おおいた公式」へ
日時:令和7年9月2日(火曜日)13時30分~
場所:第一応接室
記者会見時に配布した資料を掲載します。

「#(ハッシュタグ)大分から世界へHELLO」観光キャンペーンの中間報告について
大阪・関西万博の開催期間に合わせて、大分空港は「大分ハローキティ空港」としてサンリオのキャラクターがお出迎えする観光キャンペーンを実施中です。大分航空ターミナルの協力のもと、観光キャンペーンについてのアンケートを実施しており、その中間報告を受けましたので公表いたします。
アンケートには1,709名の方から回答いただき、そのうち1,462名が「大分ハローキティ空港」を知っていたと回答しています。
「大分ハローキティ空港」のネーミングやサンリオキャラクターのデザインについては、5点満点のうち4点以上の回答が87%以上を占めており、大変好評を得ております。
大分空港から杵築駅を経由してハーモニーランドを繋ぐ「ハーモニーライナー」を利用してみたいという方も67%と多く、また、一番お気に入りの装飾スポットは1階のフォトスポットという結果になっています。
アンケート回答者を居住地別で見ると、関東の方が732名と一番多く、その次に大分県内の方となっています。
性別では女性が73%と圧倒的に多く、女性の方がより関心が高いことが伺えます。
続いて年代では、30代が最も多く、20代、40代と続いています。空港の利用目的では一番多かったのは旅行と回答した方でした。
そのほか、自由意見欄には、「とてもかわいい。写真も撮っていい記念になった。」や、「空港装飾とハーモニーランド目的で来たが、大分県観光も楽しかった。」など誘客の効果も表れていることが伺えます。
今回のキャンペーンは国内外で大変注目を集めており、米国CNNが運営する旅行情報サイトで取り上げられたほか、台湾インフルエンサーの皆さまにも好評を得て、WEBやSNSで積極的に発信いただいています。また、サンリオキャラクターを活用することで、情報が至るところで拡散し、県内外の方々に浸透していったことから、メジャーなキャラクターの活用による効果を実感し、キャンペーンの手ごたえをつかんでいるところです。
いろんな期待も寄せられておりますが、世界でいちばん、あたたまる「大分ハローキティ空港」を皆様でお楽しみいただきたいと思います。
配 布 資 料:「OITA HELLO KITTY AIRPORT」アンケート回答状況 [PDFファイル/346KB]
大阪・関西万博に係る大分県の魅力発信について
明日9月3日(水)から5日(金)にかけて、大阪・関西万博EXPOメッセ「WASSE(ワッセ)」において、九州7県合同で催事を開催し、7県の知事がそこに集結します。
「九州の宝を世界へ~Treasure(トレジャー) Island(アイランド) KYUSHU(キュウシュウ)~」をテーマに、九州一体となって観光、食などをPRし、万博来場者に九州各県の魅力を発信します。
会場では、各県の食の魅力を詰め込んだ「九州宝弁当」や地酒等を販売します。大分県は、しいたけステーキ、はもフライ、鶏めし、安心院のスパークリングワインや梅酒を提供し、本県の「味力(みりょく)」をPRします。
また、各県が趣向を凝らして伝統芸能などを紹介するステージイベントでは、鶴崎踊や草地おどりを披露するほか、ハーモニーランドからハローキティも登場するなど、万博会場を盛り上げます。
大分県ブースでは、ハローキティや進撃の巨人など本県とゆかりのある世界的な人気コンテンツをはじめ、御鎮座1300年を迎えた宇佐神宮など県内各地の観光・地域資源の情報発信を行います。さらに、別府竹細工ワークショップや別府の街並みを再現したメタバース体験など、本県の魅力を大いにPRします。
大阪・関西万博には、連日10万人を越える方々が来場しており、この機を逃すことなく、誘客や本県の魅力発信に取り組みます。
また、万博を契機としまして、9月20日(土)と21日(日)には大分駅前広場にて、「おおいた地域博覧会フェス」を開催し、ご当地大分県において市町村と連携した万博応援イベントも実施します。
会場では、県内各地の観光素材・景観、産品、歴史・文化などをまとめた「おおいた地域資源素材集(Oita(オオイタ) Essentials(エッセンシャルズ))」をもとに、実際に18市町村イチオシの逸品に触れていただくブースを設けます。さらに、ブースを回っていただいた方に豪華県産品が当たるスタンプラリーも実施します。
また、ステージイベントでは、ハーモニーランドからハローキティが登場するほか、庄内神楽などの伝統芸能の披露や北村直登氏のライブペインティングを行います。
さらに、おおいた和牛やとり天、中津からあげ、ひゅうが丼など、県内各地の絶品グルメが味わえるブースや安心院ワイン、別府温泉クラフトビールをはじめとした、県内各地の地酒を堪能できるブースも設けます。
別府の竹細工づくりや姫島のきつね面の絵付けなどが体験できるワークショップもありますので、お子様から大人の方まで1日中楽しんでいただけるイベントとなっています。多くの国内外の皆様にお越しいただくとともに、地元大分県の皆様にも、この機会にぜひ県内各地の魅力を再発見し、各地を巡っていただきたいと思います。
配 布 資 料:大阪・関西万博に係る大分県の魅力発信(九州7県合同催事、おおいた地域博覧会) [PDFファイル/711KB]
おおいた地域博覧会フェス チラシ [PDFファイル/250KB]
カナダ・プリンスエドワードアイランド州首相の来県について
県では、大阪・関西万博を契機とした海外との交流を進めています。
その一環として、9月21日から23日までの3日間、カナダのプリンスエドワードアイランド州のロブ・ランツ首相をはじめとする州政府関係者の皆さんが来県されることになりました。
22日には県庁で、今後の交流などについてお話しする予定となっています。
プリンスエドワードアイランドは、ご存じのとおり小説「赤毛のアン」の舞台でありまして、ロブスターやルーム貝などシーフード等でも有名なところです。
シャーロットタウンが州都で、全体の人口が約15万人の州です。そのトップである首相にお越しいただけます。
小説 『赤毛のアン』を翻訳し、初めて日本に広めた村岡花子氏は、大分県出身の児童文学者・久留島武彦氏の指導を受けていたといわれています。こうした文学を通じたご縁を契機として、この度、本県とプリンスエドワードアイランド州との交流をスタートさせることとなりました。
滞在中には、玖珠町の久留島武彦記念館をはじめ、日出町のハーモニーランドや別府市の地獄めぐりなどをご案内し、大分の魅力を体感していただきます。
今回の来県を契機として、プリンスエドワードアイランド州と、大分県の交流が促され、文化や教育、経済など、さまざまな分野での協力が広がることを期待しています。
配 布 資 料:カナダ・プリンスエドワードアイランド州の概要 [PDFファイル/227KB]
こども食堂支援のためのクラウドファンディングについて
今年度も、9月1日から11月28日までの3か月間、こども食堂を支援するためのクラウドファンディングを実施いたします。
現在、県内に156か所あるこども食堂では、食事の提供はもとより、学習支援や多世代交流などさまざまな活動を行っており、こどもたちの大事な居場所となっています。
県では、こども食堂の立ち上げ時の支援や、ネットワークづくり、フードバンクを通じた食材提供などを行っていますが、ボランティアによって支えられているこども食堂が多く、物価高騰や米不足の影響など、いろいろ影響が出ております。
今年度も、500万円を目標に募集しますので、多くの県民の方々に、ご支援をいただきますとありがたいと思っております。
配 布 資 料:大分県こども食堂クラウドファンディング チラシ [PDFファイル/925KB]
「大分カーボンクレジットクラブ」の会員募集開始について
県では、脱炭素社会の実現に向けて、県民や企業と一体となり「大分県版カーボンニュートラル」の取組を進めていますが、その実現に向けては、環境に配慮した取組を行う企業が、広く評価される仕組みづくりが大切です。
このたび、株式会社大分銀行、大分県信用組合、株式会社バイウィルとともに、県内企業が導入した太陽光発電によるCO2削減価値をまとめて「J-クレジット」にする「大分カーボンクレジットクラブ」を立ち上げ、その会員募集を本日から開始しました。
「J-クレジット」は、CO2の削減量を国が認証し、その売買を可能とする制度ですが、県と金融機関が連携し、企業の太陽光発電をとりまとめてクレジット化する取組は、愛媛県に続いて全国で2例目となります。
過去2年以内に太陽光発電設備を設置しているなどの要件を満たす県内事業者が入会可能であり、会員は毎年1回、自家消費電力量を報告することで、クレジットの売却収益の還元を受けることができます。
将来的には県内の大企業等への売却を目指しており、クレジットの地産地消を通じて、大分県版カーボンニュートラルにも貢献できます。
県ではこれから、金融機関等と連携し、補助金受給企業や金融機関の顧客企業に対して加入の呼びかけを随時行っていきますので、太陽光発電設備を導入している多くの県内企業の皆さんに加入していただいて、活用いただきたいと思っております。
配 布 資 料:大分県太陽光プログラム「大分カーボンクレジットクラブ」 チラシ [PDFファイル/329KB]
記者質問
大分ハローキティ空港について
(記者)
大分ハローキティ空港について、アンケート結果からもかなり好評と窺えるが、万博期間以降も継続される可能性はあるか。
(佐藤知事)
アンケートには継続を望む声がかなり寄せられています。ただ、あくまで万博期間中ということでスタートしていますので、これから関係者の皆さんと、そうしたご意見や希望にどのように対応していくか検討していくことになると思います。
(記者)
継続に向けて、サンリオエンターテイメント側と協議はしているか。
(佐藤知事)
いえ、まだです。
(記者)
基本的には万博の閉幕により終了する予定か。
(佐藤知事)
アンケートの自由記述欄には継続を望む声がたくさんある一方で、特別感を出すためには期間限定の方が良いのではないかという意見も一部見られます。
(記者)
知事ご自身のお考えは。
(佐藤知事)
継続も含めて、関係者の皆さんと意見交換すべきではないかと思っています。
(記者)
アンケートは1,709人の回答があったとのことであるが、どのような方法で実施したのか。
(佐藤知事)
空港ロビーのフォトスポットにアンケート協力依頼のボードを設置し、そこに掲載された二次元バーコードをスマートフォン等で読み取って回答していただく形をとりました。
(記者)
サンリオキャラクターにある程度の関心がある人が回答した可能性が高いということか。
(佐藤知事)
その可能性は高いと思います。1,700人を超えており、かなり多くの方に回答いただけたと思います。
カナダ・プリンスエドワードアイランド州首相の来県について
(記者)
知事ご自身も「赤毛のアン」にたびたび触れられている印象であるが、今回の来県を機に、教育、文化、観光の面でどのような連携やタイアップをしていきたいとお考えか。
(佐藤知事)
詳細はこれからになりますが、担当部署では、すでにさまざまな協議を始めていると思います。
「赤毛のアン」は、こどもの教育にも非常に役立つ素晴らしい作品だと思いますので、教育分野での連携は可能です。また、作品の舞台となったグリーン・ゲイブルズは非常に重要な観光地になっていると聞いていますので、観光面でも連携ができたらいいと思います。
大阪・関西万博に係る大分県の魅力発信について
(記者)
九州7県合同催事の会場で、特定の知事と話をする予定はあるか。
また、九州全体で観光客の周遊を促すことについて、福岡に観光客が集中し、九州全体に流れていないという指摘もあるが、その点についてのお考えは。
(佐藤知事)
九州全体を周遊してもらう取組は非常に重要だと考えています。これは九州地方知事会議や、知事と経済界が一緒になって議論する九州地域戦略会議でも議論されていることです。その成果の一つとして、国際自転車ロードレース大会「ツール・ド・九州」の開催があります。今年は3回目を迎え、参加県も増えてきており、大分と宮崎の県をまたぎ、宮崎・大分ステージを開催することになっています。
引き続き、九州全体で連携し、魅力を発信しながら、周遊を促す取組を進めていきたいと考えています。
昨年は、福岡県と共同で「福岡・大分デスティネーションキャンペーン」を行い、大きな成果を上げました。
例えば日田市では、福岡県と県境をまたいで、日田彦山線BRTひこぼしラインが運行されていたり、酒蔵があったりします。また、祖母・傾山系を挟んで宮崎県と繋がっていますし、日田市から玖珠町・九重町、竹田市にかけては熊本県との繋がりもあります。このように、県境を越えた広がりを持って取り組んでいくことが重要だと考えています。他県の知事も同様の考えではないかと思います。
(記者)
改めてどのような点をPRしていきたいとお考えか。また、今後の県内観光振興にどのように繋げていきたいか。
(佐藤知事)
万博には現在、1日約10万人もの方が来場されており、外国の方も非常に多く来場されています。この場所で、九州各県が一体となって魅力を発信できるのは大きなチャンスです。今年の夏はインバウンドが厳しい状況でしたが、今後さらに増えるであろう外国人観光客への魅力発信に繋げていきたいと考えています。
食や観光、そして鶴崎踊や草地おどりのような伝統芸能、歴史・文化など、さまざまな魅力をPRします。先日作成した「おおいた地域資源素材集」も5千部ほど用意しており、英語でも記載しているので、これを見て「今度ぜひ大分に行ってみたい」と思ってもらえるよう、一人でも多くの方に関心を持っていただけたらと思っています。
(記者)
万博で展示されているSkyDrive社の空飛ぶクルマへの期待感は。
(佐藤知事)
先週、私も万博会場に行き、SkyDrive社のデモ飛行を見てきました。その後、機体を近くで見学させていただきました。
大分県は、JR九州、SkyDrive社の3者で連携協定を結んでいます。SkyDrive社の発表によると、2028年度頃には別府湾での周遊から始めたいとのことです。将来的には別府と湯布院を結ぶ観光ルートの実用化を目指したいと述べられており、実現が遠い将来ではないという期待を持ちました。実用化の一歩手前まで来ていることを実感しました。
「大分カーボンクレジットクラブ」の会員募集開始について
(記者)
クレジット売却により、どれくらいの発電量でいくらくらいの収益が見込めるのか。
(佐藤知事)
概算ですが、例えば中小企業が設置した50kWの太陽光発電の場合、年間で2~3万円くらいの収益になるイメージです。それほど大きくはありませんが、何もせずに放っておけば収益はゼロですし、クレジットの価格は上がったり下がったりする可能性もあります。現時点では、必要経費を除くとそれくらいの収益になると試算しています。
(記者)
県内企業が取り組む意義を改めてご教示願いたい。
(佐藤知事)
この取組は2つの意義があると考えています。一つは、このような活動を通して環境に優しい企業活動を行うという意識を高めることです。もう一つは、J-クレジットを活用することで、それが収益として返ってくる仕組みがあることです。こうした金融機関と連携した取組は全国で2例目であり、大分県が率先してこのような仕組みを作ることで、県全体でカーボンニュートラルを目指す「大分県版カーボンニュートラル」の達成に繋げていきたいと考えています。中小企業の皆さんにもその一翼を担っていただければ幸いです。
こども食堂支援のためのクラウドファンディングについて
(記者)
昨年の寄附金がどのように活用されたのか、また県民に向けて改めて呼びかけをお願いしたい。
(佐藤知事)
昨年は、希望した116か所のこども食堂に、平均約5万円を配分することができました。主に運営費や食材費に充てていただいたと聞いています。今年はお米を含め食料費がさらに上がっていますので、そういった部分にも活用できると思います。また、レクリエーション費用や、野菜作り体験活動に使われた例もあります。配分したお金は自由に活用してもらっているので、有意義に使われていると思います。
こども食堂は、こどもたちの居場所であり、交流の場、生きがいを見つける場、そしてみんなでこどもを育てていこうという場にもなっています。しかし、ほとんどのこども食堂が、ボランティアの方々が中心となって運営されているため、資金的に厳しいところも多いのが現状です。ぜひ、このクラウドファンディングにご参加いただき、ご支援いただけるとありがたいです。
日米共同訓練について
(記者)
日出生台演習場などで、今月11日から日米共同訓練が予定されており、これに先立ち、オスプレイの飛来も予定されていると伺っている。
現在、日米で離島防衛を想定した訓練が増えており、日出生台演習場の利用が今後さらに増えるのではないかという懸念が地元から出ている。
知事はこうした懸念や認識をお持ちか。また、県として行っている対応は。
(佐藤知事)
九州防衛局長には、今年も尾野副知事から申し入れを行いました。演習を実施するにあたっては、何よりも県民の皆さんの安全と安心の確保が重要です。そのためには、どのように訓練を行うか説明いただくこと、そして、これまで結んできた協定をしっかり守っていただくことが必要です。協定に沿った訓練の実施と、情報の開示を引き続き強く求めていきたいと考えています。
(記者)
日出生台演習場などでの訓練が増えているという話もあるが、そうした負担感の変化は感じているか。
(佐藤知事)
国際情勢の変化に対応するため、防衛省や自衛隊がさまざまな検討をしながら訓練計画を立てていると思いますが、訓練が増えているという実感はあります。
やはり、県民の皆さんにしっかり説明し、必要な情報を開示していくことが何より大事だと考えています。県民の皆さんからも懸念の声が寄せられていますので、九州防衛局にそれらをしっかり伝え、不安を少しでも解消し、軽減するための取組を続けていきたいです。
(記者)
訓練が増えているという認識がある一方で、飛来情報などの情報公開がこれまでほどされていないという声も聞かれるが、県の考えは。
(佐藤知事)
防衛上の機密もあると思いますが、情報共有については、以前から約束していただいていますので、引き続き強く求めていきたいと考えています。
公務員の兼業について
(記者)
人手不足対策として、県職員が兼業するケースが全国的に増えている。大分県の県職員の兼業・副業に対する考えは。
(総務部長)
制度上、規定に沿う場合は許可できます。そのような職員がいれば、その都度、適切に判断していくというスタンスです。
最低賃金について
(記者)
審議会の専門部会による審議が難航している状況だと思うが、知事の所感は。
(佐藤知事)
物価と賃金の好循環を実現していくことは大変重要です。物価が上がる一方で賃金が上がらないと、生活は厳しくなります。また、企業にとっても人材確保は重要であり、そのためには待遇を良くし、賃金を上げていくことが必要です。
そうした意味で、最低賃金がしっかりと確保されていくことは重要だと思います。しかし、特に中小企業などは、エネルギー費や原材料費、そして人件費の上昇に直面しながらも、販売価格に転嫁できないという現実の悩みを抱えています。
県としては、賃上げを促進するため、さまざまな施策に取り組んでいます。例えば、12項目の賃上げ枠を設けましたし、4日に開会する議会には、中小企業等業務改善支援事業において業務改善奨励金に重点枠を創設し、最低賃金改定幅を超えて最低賃金を引き上げた場合に、補助率を2分の1から3分の2に拡充できるように、補正予算を提出する予定です。こうした制度設計により、賃上げをより強く促していきたいと考えています。
これだけでは不十分なため、価格転嫁も促進するため、政労使会議では、大企業に中小企業の価格転嫁を受け入れるよう要請したりしています。また、公共契約において、賃金部分の適正化や、契約期間中に賃金が上がった場合に単価を見直すスライド制を導入したりしています。
賃上げの環境を整えることは、行政の役割であり責任でもありますし、賃金をしっかり上げていくことが社会から望まれていることだと思います。
(記者)
中央審議会から示されている目安額に対して、どのような額になるのが望ましいとお考えか。
(佐藤知事)
少しでも、上げられるところまで上げてもらうのが望ましいと思います。昨年の改定で55円上がり、954円になりました。このままいけば、1,000円を超える額になるだろうと思います。
審議が難航しているのは、先ほど申し上げたように、厳しい経営環境の中でどう賃上げをしていくかという経営者の大きな悩みがあるためで、そのために労使間でしっかり議論されているものと認識しています。
スマートフォンの適正使用について
(記者)
愛知県豊明市で、スマートフォン等の適正使用推進条例の制定が議会にかけられているようだが、この条例に対する知事の所感は。
(佐藤知事)
そのような検討がされるほどスマートフォンが普及したのだな、というのが正直な感想です。
私の考えとしては、一個人の行動を条例などで縛ることにはあまり賛成ではありません。ただ、このくらいまでなら健康的だが、これ以上使うと良くないといったガイドラインは、重要なのかもしれません。
現時点では県庁内で具体的な議論はしていませんが、今後、市町村や県でもそうした議論が出てくるかもしれませんので、動きを注視していきたいです。
(記者)
豊明市の条例では、余暇の時間でスマートフォンの利用を2時間程度とすることが盛り込まれているようであるが、知事ご自身は余暇の時間でどれくらいスマートフォンを利用しているか。
(佐藤知事)
2時間も使っていない気がしますが、ニュースを見たり、調べものをしたりと結構使っているかもしれません。おそらく、他の人と比べて特別に多く使っているということはないと思います。
(記者)
YouTubeで動画を見たりすることはあるか。
(佐藤知事)
はい。音楽を聴いていて、「この曲を聴いてみたい」と思った時に検索すると、たいていYouTubeで見つかるので利用しています。
広域リージョン連携推進要綱について
(記者)
都道府県域を超えた広域リージョン連携について、今日午前中に総務省が要綱を発表したようであるが、現時点での知事の受け止めは。
(佐藤知事)
まだ正式な情報は入手していませんが、報道で九州が事例の一つとして挙げられていると聞きました。以前から九州地方知事会議や九州地域戦略会議で、県の枠を超えた連携について議論を重ねてきました。例えば、半導体人材の育成や広域交通ネットワークの整備などです。
そうした都道府県域を超えた取組に対して、交付金を活用して支援することが政府で検討されていることは、ひとつのあり方だと思います。例えば、ツール・ド・九州のような、九州全体の振興などに交付金が使えるようになると非常に良いと思います。
一方で、地方創生の議論をするのであれば、国にしかできないことはたくさんありますので、まずはそこに力を入れてほしいと思います。そして、県をまたいだ取組や、九州が一体となった取組、さらには九州と四国が一体となった取組などを取り上げてもらえると嬉しいです。そのような議論も合わせて行っていただければと思います。




