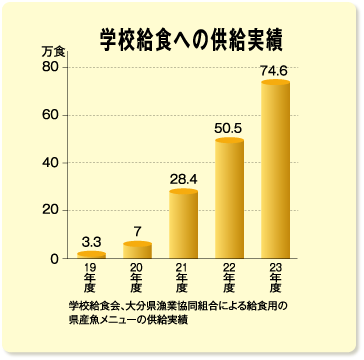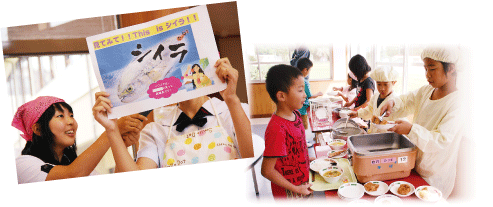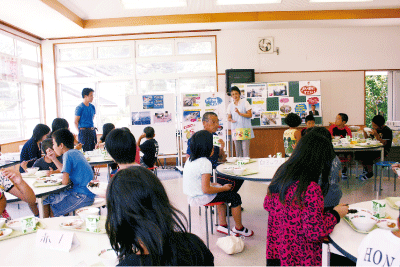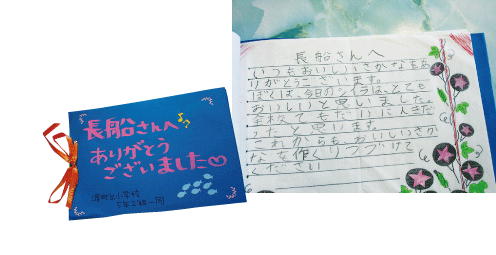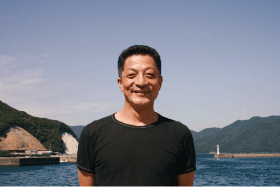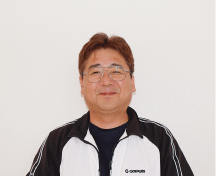本文
たくさん食べよう県産魚!
たくさん食べよう県産魚!
ライフスタイルや食生活の多様化に伴い、家庭で食べられる魚の量が年々減少しています。豊かな漁場に恵まれた大分県では、地元で獲れた魚を地元で食べてもらうためにさまざまな取り組みが行われています。今回の特集では、魚好きの子どもたちを増やすために、県産魚を使った献立を積極的に取り入れている学校給食の現場を追いました。

給食でおおいたの魚を食べる
「家庭で魚を食べてもらうには、『学校で食べた魚がおいしかったから家でも食べたい』と言う子どもが増えることも重要です。そこで、学校給食では魚を使った献立を積極的に取り入れています。魚には体をつくるために欠かせない良質なタンパク質などの栄養素が含まれているからです。また、魚を通じて子どもたちに地元のことを知ってほしいと思い、できるだけ県産魚を使っています」と語るのは、給食の献立作成や食育の推進をするために市内の小学校を巡回指導している栄養教諭の高野 美幸先生です。 以前は、限られた給食費の中で県産魚を使うのは厳しい状況でした。平成21年度から大分県漁業協同組合、水産加工業者、大分県学校栄養士研究会、公益財団法人大分県学校給食会が協力して供給体制を整ったことで、給食での使用が実現できました。
こうした中で、佐伯市では「さいき活き活き献立の日」を定め、定期的に佐伯市産の食材を使った献立を市内の小中学校などに提供しています。
|
↑高野 美幸先生(渡町台小学校)と色宮小学校の生徒たち
↑給食に使われている佐伯市産の魚について説明する高野先生と生産者
|
一方、シイラを提供し、加工処理をした大分県漁業協同組合 米水津水産加工処理施設の長船 長茂(おさふね ちょうしげ)工場長は「子どもたちに地元で取れた魚を食べてほしいと思っているので、学校給食で使ってもらえるのは嬉しいです。旬の魚が一番おいしく栄養価も高いので、ブリやアジ、ハモなど時期に応じて提供しています。学校に行った時に聞いた『おかわり!』の声や『おいしい』と言う時の子どもたちの笑顔が励みになっています。県内の子どもたちにたくさん魚を食べてもらいたいです」と微笑みました。
今後も県産魚を使った献立が増えることで、大分の海の恵みに感謝をしながら魚をおいしく食べる子どもたちが増えることを期待します。 |
↑大分県漁業協同組合 米水津水産加工処理施設 工場長 長船 長茂さん |
自分でさばくともっと魚が好きになる
大分県漁業協同組合女性部では、子どもたちに魚に親しんでもらおうと、県内各地でお魚教室を開催しています。今回は、臼杵支店の女性部が行った「臼杵っこ料理教室」を訪ねました。支部長の廣戸とよ子さんらの指導のもと、子どもたちは真剣な表情でタチウオをさばいていました。「自分でさばくことで、食材のありがたさが実感できます」と廣戸さんは言います。 |
子どもにタチウオのさばき方を教える廣戸 とよ子さん |
もったいない精神で有効活用
くろめは、大分市佐賀関で昔から親しまれている海藻です。そのくろめを棒状に巻く「巻きくろめ」を作る時に出る端切れに目をつけたのは、大分市水産物流加工協議会の大分県漁業協同組合佐賀関支店 出田 要二(いでた ようじ)さんです。
|
大分県漁業協同組合 佐賀関支店 出田 要二さん |