本文
大分県の特産品(乾しいたけ)
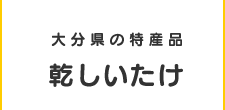

1.いつから生産され始めたの?
「しいたけ栽培はおよそ400年ほど前の江戸時代前期に、大分県で始まったんだよ。」
しいたけ栽培はおよそ400年ほど前の江戸時代前期に始まったと言われています。豊後の国千怒浦(現津久見市千怒)出身の源兵衛さんが岡藩宇目郷(佐伯市宇目)炭焼きをしていたとき巻き付いたカズラをナタで切った後にしいたけが発生しているのを見つけたと言われています。切った木に傷をつける「ナタ目栽培」が始まりました。自然界に浮遊している胞子が付着するのを待つという原始的な方法です。
人工的に種菌を植え付ける方法が開発されたのは60年ほど前で、それまでは自然の成り行きまかせでした。

出身地の津久見市と佐伯市宇目にある源兵衛さんの像
2.生産量や生産額などはどのくらい?
「大分県の乾しいたけ生産量は日本一!」
大分県の乾しいたけ生産量は日本全体の生産量のおよそ1/3で、1,401トン(2011年の生産量)で、日本一の生産量を誇ります。
また、毎年東京などで開かれる品質や品揃えを競う全国乾椎茸品評会では13年連続45回の団体優勝を果たしており、大分県産の乾しいたけは品質においても高い評価を得ています。
3.どこで生産されているの?
「乾しいたけは県内全域で生産されているんだよ。」
大分県では、県内全域で乾しいたけ栽培が行われていますが、生産量の多いところは竹田市や豊後大野市、日田市、国東市となっています。
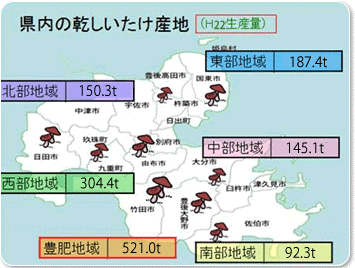
4.どうやって生産するの?
「しいたけの駒打ち、みんなも体験したこと、あるかな?」| (1) | 原木の伐採(11月) 原木となるクヌギやコナラなどを11月中旬に伐採し、葉をつけたまま枯らします。 |

| (2) | 原木の玉切り(1月) 伐採してから2カ月くらいたってから、1m程度に切断(玉切り)します。 |

| (3) | 植菌(1~3月) 玉切った原木に電気ドリルで植え穴をあけ、種駒を接種します。 |

| (4) | 原木の伏せ込み(2年間) 種駒を接種した原木は、しいたけ菌糸が伸びやすい環境に伏せ込みます。 |

| (5) | ほだ起こし 伏せ込んで2夏経過後の秋にしいたけの発生に適した場所(ほだ場)に移します。 |

| (6) | しいたけの発生と採取 しいたけは主に春と秋に発生します。しいたけが適当な大きさになったら、柄の根元の部分を軽くねじるようにして採取します。 |

| (7) | しいたけの乾燥 しいたけ乾燥機で乾燥すれば、乾しいたけのできあがりです。 |

5.おいしい食べ方は?
「実は種類がある乾しいたけ。おいしい食べ方を研究してね。」
しいたけは、傘の開き具合、厚さによって「どんこ」、「こうこ」、「こうしん」と呼ばれ、それぞれおいしい食べ方が異なります。
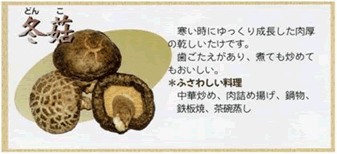
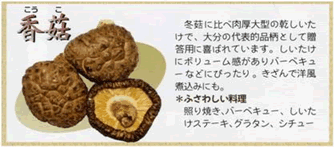
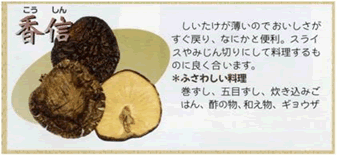
こんなこともあるよ
「森林を守り育てる原木しいたけの栽培」
クヌギやコナラなどの広葉樹は、伐採した切り株からまた芽が出てきて若い林となります。この広葉樹をしいたけ原木として活用することは、森林の新陳代謝を促し活力を高めるとともに、CO2削減にもつながっています。
また、山里の林は、しいたけを発生させる”ほだ場”として活用されており、しいたけの発生のためには枝打ちや間伐などの手入れが必要です。手入れされた林は木の生長が良くなり、多くの機能を持った良い林に生き返らせることができます。
大分産原木しいたけを食べることは、山村に住む生産者のなによりの支援になり、それが大分の森林を守り育てることにつながるのです。




