本文
大分県の特産品(くるまえび)
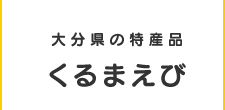

1.いつから生産され始めたの?
「くるまえびの養殖が始まったのは1965年頃なんだ。」
くるまえびは、日本ではいせえびと並んで高級えびの代表として扱われています。そのため、昔から重要な食材として漁獲されていました。また、えび類では最も早く養殖技術が確立され、1965年頃からは養殖も盛んに行われるようになりました。

くるまえび
2.生産量や生産額などはどのくらい?
「大分県の天然くるまえび生産量は全国第2位!養殖も盛んで、全国第6位なんだよ!」
大分県の2009年の漁獲量は、全国第2位の119トンで、漁業生産額は587百万円となっています。大分県では、毎年夏頃に、県内すべての海域で、漁師さんがくるまえびの種苗(赤ちゃん)を大量に放流しています。この活動も、全国2位を誇る漁獲量を支えています。また、姫島などでは養殖も行われており、2009年には全国第6位の75トンを生産しています。

くるまえび放流用の囲い網(宇佐市)
3.どこで生産されているの?
「大分県内では宇佐市や姫島村で漁が行われています。」
日本では北海道南部以南から分布していますが、漁獲量が多い順に、愛媛県、大分県、愛知県、福岡県で多く漁獲され、大分県内では、宇佐市、姫島村、杵築市で主に漁獲されます。
4.どうやって生産されているの?
「小型底引き網や流し刺し網漁が行われています。」
小型底びき網漁業と流し刺し網漁業で主に漁獲されます。小型底びき網漁業とは、漁船を使って海底まで沈めた網を引っ張って、海底にいる魚やえびなどを獲る漁業です。周防灘や別府湾では、この漁法でくるまえびが多く獲られています。流し刺し網漁業とは、網を海中にしばらく流しておき、そこを通り過ぎようとする魚やえびをからめとる漁法で、姫島周辺で盛んです。

小型底引き網漁業の水揚げ
5.おいしい食べ方は?
「鮮度が落ちるのが早いから、新鮮なうちに味わって!」
旬は7月~12月で、生きたまま殻をむき、そのまま刺身として食べる「おどり食い」をはじめとして、天ぷら、塩焼き、酒蒸しなどにします。くるまえびは、甘みを感じさせるアミノ酸がえび類の中で一番多く、新鮮な物ほどとても甘くてプリッとした食感が格別です。えびは鮮度が落ちるのが早いので、生きたものを食べるのが一番おいしく食べるコツです。

くるまえびの刺身

くるまえびの塩焼き
こんなこともあるよ
「くるまえびの成長」
くるまえびは成長がとても早く、夏場に全長3cmくらいの種苗を放流すると、その年の秋には全長10cm以上の漁獲サイズになります。
「姫島車えび祭」
姫島村では、毎年10月に「姫島車えび祭り」が開かれ、島の漁師とその家族が腕をふるい、島にある4つの港でそれぞれ新鮮な料理や加工品がふるわれます。
「鮮度を保つためには」
くるまえびをおが屑に入れると、海水が無くても数日間生き続けることができるので、生きたまま送る場合はおが屑に入れることが多いです。




