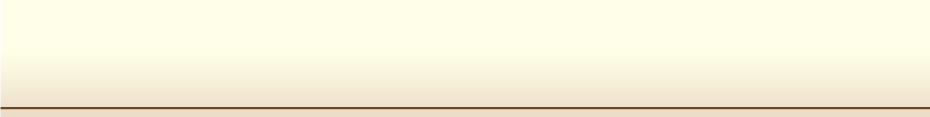本文
特集1 移住・定住を支援します! ~おおいた暮らしの第一歩~
特集1 移住・定住を支援します!
~おおいた暮らしの第一歩~
大分県の人口は、108万5千人(令和6年10月1日現在)で、年1万1千人のペースで減少しています。
現在の人口構成から当面、高齢化・少子化の進行は避けられない状況です。そのため県では、UIJターンなどによる人口増を目指し、県内へ移住・定住しやすい環境づくりに取り組んでいます。
県内への移住支援策
令和6年度に、県の移住支援施策等を活用して、県外から移住した方は、1,746人となり、5年連続で過去最多を更新しました。県や市町村では移住を後押しするさまざまな支援策を展開して、移住者数増に取り組んでいます。
特に県では、移住を考えている方に向けて、仕事や子育て、生活のサポートなど、充実した移住支援制度を用意しています。今回は、県・市町村が提供する移住・定住の支援策について、先輩移住者のインタビューを交えて紹介します。
北海道から大分へ
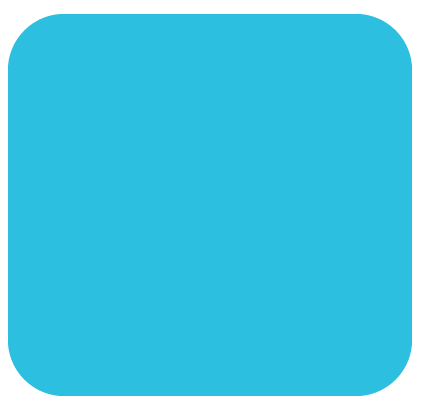 大分県の支援策を活用し県内のIT企業に就職
大分県の支援策を活用し県内のIT企業に就職
植野 翔也さん

Q1 移住のきっかけを教えてください
前職は中学校の教師です。もともとパソコンやゲームが好きで、独学でエンジニアの勉強をしていたところ、「おおいたIT移住プロジェクト」の広告を目にして、転職と移住を具体的に考えるようになりました。「スクーリング制度」を活用して大分を訪れた際、地域や企業の雰囲気を直接感じ、支援体制を確認できたことも、挑戦を後押ししてくれました。
Q2 現在の仕事について教えてください
大分市のIT企業で、Webアプリケーションや顧客管理ツールの開発に携わっています。十分な研修期間があり、未経験でもなじみやすい環境でした。知り合いの全くいない土地での新生活は不安でしたが、移住プロジェクトを通じて知り合った方々と今でも交流が続いており、教員時代より人間関係の幅が広がったと感じています。
Q3 大分での暮らしはいかがですか
都会過ぎず田舎過ぎず、適度な規模感で人との関わりが持ちやすい街です。移住者を温かく歓迎してくれる雰囲気があり、時には職場の先輩方と地元サッカーチームの観戦に行くことも。仕事にも慣れてきたので、今後は教員経験を生かして後輩育成に携わったり、他地域の方に移住の楽しさを広めたり、さまざまな活動に挑戦してみたいです。
Q4 移住を考えている方にメッセージをお願いします
環境が大きく変わるとなると、不安な気持ちになってしまうと思います。私が意識していたことは、前向きな気持ちで臨むということでした。マイナスに考えず、ワクワクすることを考えるとステキな移住ライフが送れるのではないかと思います。
おおいたIT移住プロジェクトについて
「おおいたIT移住プロジェクト」では、県内への移住を希望する方に、仕事の確保につながるIT技術の習得と就職支援などのサポートを行っています。
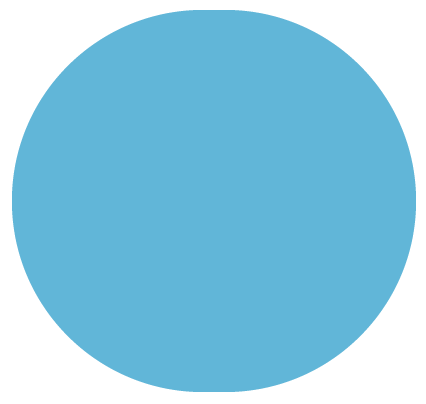 対 象 者/大分県に移住し、IT企業への就職やフリーランス起業を希望する方
対 象 者/大分県に移住し、IT企業への就職やフリーランス起業を希望する方
※転勤・入学による移住者は対象外、直近1年間は大分県外に住民票があることが条件
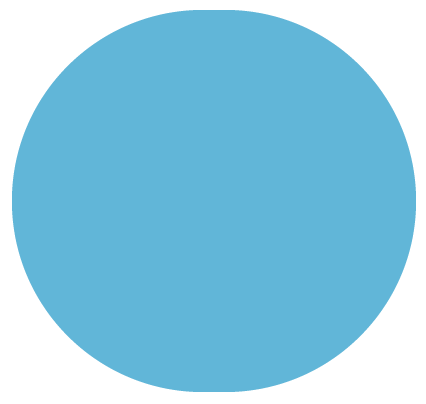 支援内容/IT技術スクール受講費用(無料)
支援内容/IT技術スクール受講費用(無料)
Webエンジニア、Webデザイナーなど未経験者でも学べるカリキュラムを提供
※一部実費負担あり
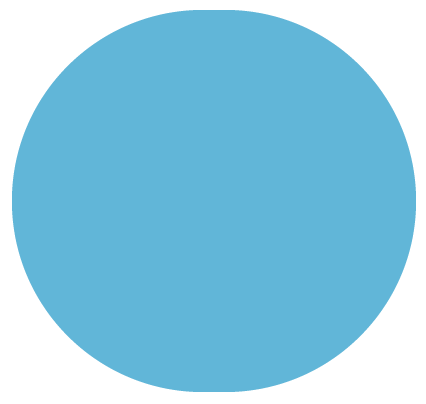 就職・転職支援/求人情報の提供、面接対策などを実施。
就職・転職支援/求人情報の提供、面接対策などを実施。
起業に挑戦される場合は、必要な事務手続きの支援や案件獲得のサポートを実施
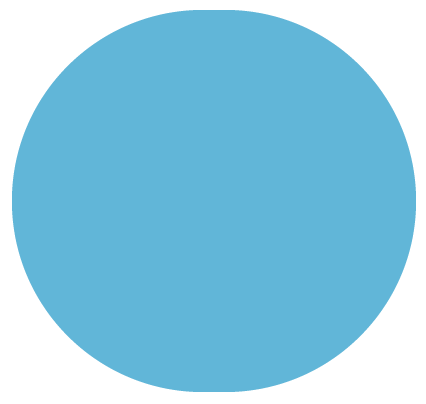 応募締切/12月26日(金)
応募締切/12月26日(金)
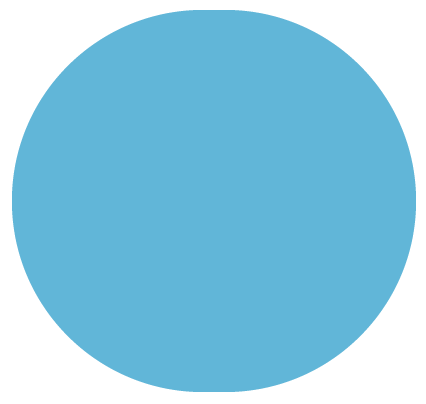 注意事項
注意事項
・参加条件として、令和8年5月15日までに移住していただく必要があります。
・参加後に辞退される場合は、受講費用を返還していただきます。
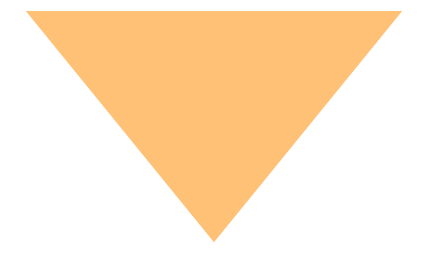 詳細はこちらから
詳細はこちらから
https://migration.oita-creative.jp/
幼い頃から憧れていた田舎暮らし 多様な価値観に触れて私らしく輝く
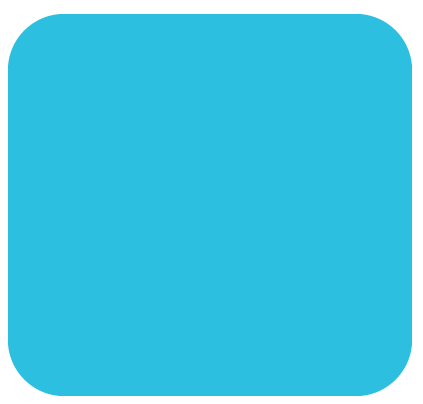 浅野 千愛さん
浅野 千愛さん

Q1 移住のきっかけを教えてください
私は東京都練馬区で育ったのですが、両親の生まれも東京なので、自分には「田舎のおじいちゃん、おばあちゃんの家」という場所がなくて。だから帰省の話を嬉しそうに話す友達をいつも羨ましいと思っていました。そして実際に移住をしようと決めたのが離婚した30歳のとき。結婚後はこのまま関東に住み続けるんだろうな…と考えていたのですが、離婚を機に「これからは好きな場所に住むことができる! 挑戦のタイミングだ」と前向きに考えました。
Q2 移住後のお仕事について教えてください
最初の3年間は地域おこし協力隊として働き、主に空き家バンクや移住の担当をしていました。さらに国東市国見町で活動する作家さんの動画撮影や、田んぼで古代米を育てたりもしました。田植えは私が長年挑戦してみたかったことの1つだったので嬉しかったですね。現在は国東市観光協会に就職して3年目になります。地域おこし協力隊として濃密に過ごした3年間の経験がとても役立っています。
また新たな学びも得つつ、日々国東のことを考え取り組んでいます。
Q3 理想とのギャップを受け、帰りたいと思ったことは?
一度もありません。周りの人達の影響もあると思いますが、移住して暮らしを楽しんでいる人たちはみんな「ないものを数える」ということをしません。価値観の問題もありますが、この考え方が移住のポイントだとも私は感じていて。以前の暮らしと現状を比べ、ないものを数えている人は新たな土地に馴染むことも難しいのかなと思います。
Q4 移住を考えている方にメッセージをお願いします
移住に興味があるなら、全員してみたら良いのに! と思います。大切なのは、ないものを数えずに楽しむこと。移住を検討されている多くの方と関わってきましたが、ものごとを引き算で考える人は家探しも一向に進まない傾向にありました。その後も壁にぶつかるパターンが多かったように感じます。その場所を楽しみ、価値観を受け入れることができると、田舎暮らしはとても楽しいと思います。
地域おこし協力隊について
移住方法の選択肢の一つとして、地域おこし協力隊制度があります。都市部から過疎地域などの条件不利地域に移住し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援など「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を促す国の制度です。
隊員としての活動期間はおおむね1年から3年で、県内では、74人の方が地域おこし協力隊として活動しています(令和7年4月1日時点)。
また本県は、直近5年間(平成31年4月1日~令和6年3月31日)に活動期間が終了した隊員の地域への定住率が73.0%で、九州で最も高くなっています。
隊員の募集については、各市町村にお問い合わせください。
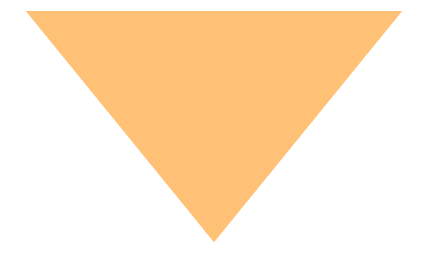 移住に関するお問い合わせ・オンライン移住相談はこちら
移住に関するお問い合わせ・オンライン移住相談はこちら
大分移住ポータルサイト『おおいた暮らしの第一歩』
https://www.iju-oita.jp/
移住先での住まいの確保について
移住を考える際、住まいの確保は移住者にとって大事なポイントです。
県では、家の新築・購入を考える若者世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)・子育て世帯(18歳未満のこどもがいる世帯)を対象に、無料で相談ができる窓口を開設しています。オンラインや電話で気軽に相談可能で、相談内容に応じて行政書士や不動産業者などの専門家をご紹介します。
〇相談例
・購入したい土地に農地が含まれており、必要な手続きが分からない
・登記などの権利情報が不明で契約ができない
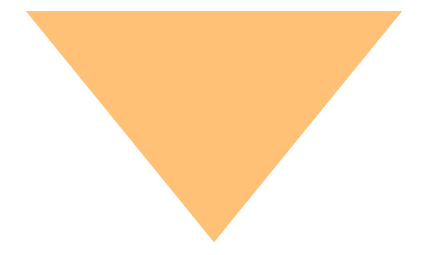 詳しくはこちら
詳しくはこちら
https://www.pref.oita.jp/soshiki/10112/teijusoudan.html
(問) おおいた創生推進課 097-506-2038